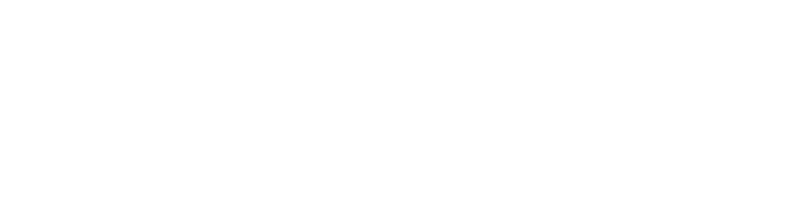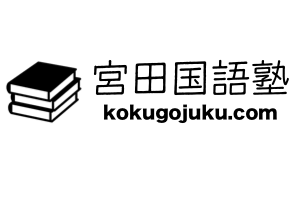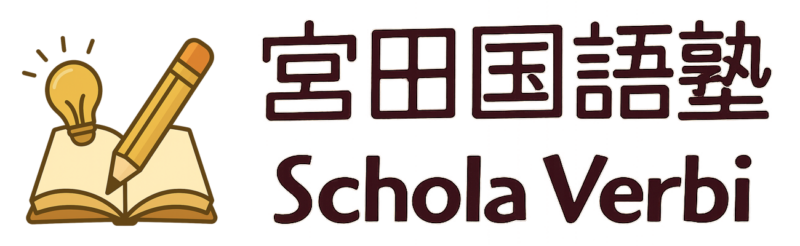8月もそろそろ終わりですね。毎年のことですが、この時期は朝から晩まで忙殺されており、ブログを書くこともままなりません。9月からは平常運転に戻る予定。
さて、今日は久々に、国語入試問題から興味深い文章をご紹介したいと思います。神戸女学院中で平成20年度に出題された、鷲田清一『悲鳴をあげる身体』からの一節です。
鷲田清一氏の文章はとても説得力があって、個人的に好きなんですが、小学生に読ませるのはなかなか酷な話。こういう大人向きの文章を平気で出題してくるのは、さすがの神戸女学院中というところです。
「赤ちゃん・子どもは家庭や学校でどのようなことを体験すべきか」というのが文章のテーマなんですが、「幼稚園」では「他者への想像力」「他者への根源的な信頼」が学ばれるべき最も重要なことだと述べられます。平たく言えば「他者への思いやり」を学ぶということですね。
では、その前段階である「家庭」では何を体験すべきなのか。ここからは鷲田清一氏の文章を引用します。
(鷲田清一『悲鳴をあげる身体』から引用)
さて家庭では、ひとは、<信頼>のさらにその基礎となるものを学ぶ。というより、からだで深く憶える。<親密さ>という感情である。
家庭という場所、そこでひとはいわば無条件で他人の世話を享ける。言うことを聞いたからとか、おりこうさんにしたらとかいった理由や条件なしに、自分がただここにいるという、ただそういう理由だけで世話をしてもらった経験がたいていのひとにはある。
(中略)(食べこぼしの処理、大便の世話などが例示される)
そういう「存在の世話」を、いかなる条件や留保もつけずにしてもらった経験が、将来自分がどれほど他人を憎むことになろうとも、最後のぎりぎりのところでひとへの<信頼>を失わないでいさせてくれる。そういう人生への肯定感情がなければ、ひとは苦しみが堆積するなかで、最終的に、死なないでいる理由をもちえないだろうと思われる。
あるいは、生きることのプライドを、追いつめられたぎりぎりのところでもてるかどうかは、じぶんが無条件に肯定された経験をもっているかどうか、わたしがわたしであるというだけでぜんぶ認められ世話されたことがあるかどうかにかかっていると言い換えてもいい。(中略) こういう経験がないと、一生どこか欠乏感をもってしか生きられない。(中略) 人間の尊厳とは最終的にそういう経験を幼いときにもてたかどうかにかかっているとは言えないだろうか。
本当にその通りだと思います。
親の子に対する愛は無償の愛。何らかの見返りを求める人なんて普通はいません。我が子であること、その一事だけによって、親は全力で愛情を注ぐわけです。そして、その愛情(=親密さ)が子の人間としてのもっとも重要な基礎を築く。とても重要な指摘だと思います。
少し話は逸れるかもしれませんが、欧米では比較的早くから子離れを意識するのが常識だと聞いたことがあります(生後間もない頃から親と別のベッドで寝かせるなど)。それに反して、アジアやアフリカでは、親とのスキンシップがかなり重要視され、子どもと親がベタベタする期間が長いというデータがあります。
私は純然たるアジア人ですので、赤ちゃんとはいくらでもベタベタしていればいいと思うんですよね。そして赤ちゃんのことは何から何までやってやる。それが子としての権利でもあり、親としての権利でもある気がします。
そんな風に生後間もない頃から無条件に大切にされれば(チヤホヤ・ベタベタされれば)、無意識下に「自分は大切にされるに値するものだ」「人生は素晴らしいものだ」ということが刷り込まれる。そうした感情は、一生その人を支えてくれる。そして、自分が大切なものであるならば、他人だって同じく大切なものなんだと自然に体得される。
それでバラ色の世界が現出する、なんて短絡的なことを言うつもりはありません。が、一人一人が人生への肯定感情を持てば、少なくとも、自ら命を絶つ人の数は少なくなるのではないか。
こうした無条件の愛を注がれない子どもは、本当に可哀想だと思います。鷲田清一氏が指摘するように、一生にわたって欠乏感を抱き続けることになるでしょう。大人になってから、その欠乏感を埋めることはできません。
私の乏しい経験からは、つながりが深い親子の方が、比較的自然に子離れ親離れしてゆくように思うんですが、どうでしょうか。明言する自信はありませんが……。