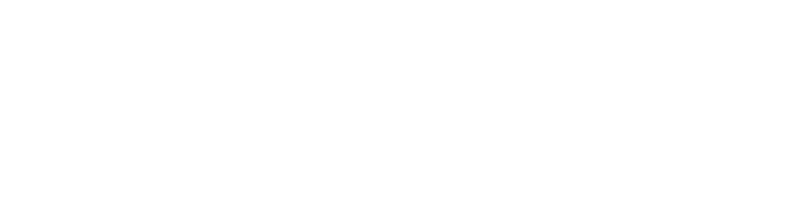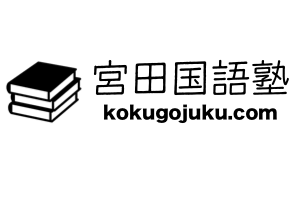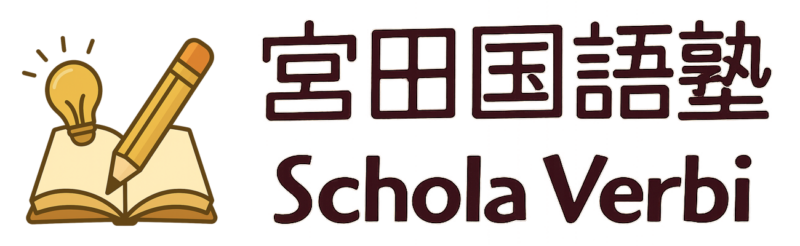そういう時代なのかもしれませんが、昔に比べ、ごく短期間で効果や答えを得ることが求められるようになったと思います。それもあらゆる場面で。
もちろん、それが妥当な場合もあろうとは思いますが、なんだか行きすぎている気がするんですよね。おそらく、背景にはインターネット・スマートフォン・検索サービス等の一般化・高速化があるんでしょうが、即座に答えや結論が得られることが本当に「善」なのか。
私達のように、子供たちの読解力や国語力を伸ばそうと日夜奮闘している立場からすると、「短期間で効果が現われること」を求め過ぎると、どうも子供たちの学力向上を阻害してしまうように思います。
もちろん、私達も生徒さんの学力を出来るだけ速やかに伸ばしたいとは思っているんです。思っているんですが、事を急ぎすぎると結局何も身に付かないことになりかねません。読解って、人の書いた話をじっくりと読んで、着実に理解するところから始まるわけですから。
スピードを上げても文章内容をしっかり理解できるというのなら構いませんが、それは小学生の場合、かなり学力の高い子でも至難の業。スピードと理解がトレードオフの関係になりやすい。
このブログでも何度書いたか分かりませんが、どちらを優先するかと言えば、もちろん精読やしっかりとした理解の方。スピードよりも圧倒的に精読が大事です。精読できれば自然に速度は上がってきます。「ニワトリと卵」のように「どちらが先なのか分からない」話ではありません。
難関中学の入試問題を見てもらうとお分かりいただけるかと思いますが、甘い読みで点数が取れるほどイージーな問題はありません。求められているのは「甘い読みの速読」ではなく、「(ある程度の速度を伴った)精読」です。
かつて灘中に伝説的な国語教師がいらっしゃって、1年掛けて1冊の小説を読むという授業をなさっていたという話があります。確か、中勘助の『銀の匙』を教材にされていたと思うんですが(センスいい!)、それほど大部の小説ではありません。それを1年で1冊です。
もちろん、極めて学力や理解力の高い中学生を相手にした授業であり、すべての中学生にそうした授業が成立するとは私も考えません。ただ、本当に学力を高める授業や勉強というのはそういうものであろうと思います。
深く深く文章を読み込む。それは具体的な一個の作品を突き詰めていくことです。しかし同時に、本当に突き詰めてゆけば、具体に止まるものではなく、本当の意味での抽象化能力に行き着く。ちょっと分かりにくいでしょうか。助けを借りながらでも、自分の力で深く読み込んでいけば、その過程で(その小説だけでなく)「あらゆる」文章を読み取る力・つかみ取る力が身に付く。
読解力の高い人には「何を当たり前のことを言っているのだ」と思われるでしょうが、この考え、なかなか理解されにくい場合があります。
特に幼児教室などで、大量のプリントをやるようなスタイルになれ親しんできた子たち(場合によっては保護者様も)。スピードを上げて量をこなすことが「勉強」だと、固く信じ込んでいます。
そうした「勉強」をしてきた生徒さんに、試しに読解する文章と問題を渡すと、ものすごい速さで問題を解き始めます。よくあるのはこんなパターン。
「ちょっと待って。ちゃんと文章のほうは読んだかな?問題はそれからにしようね。」
「うん、読んだよ。」
明らかに読めていないんですが、とりあえず問題を解かせてみます。
「じゃあ先生の方で丸付けをしてみるね。」
ほぼ全問不正解。全く文章の理解がなされていないわけですから当然です。私達の求める「読む」と彼・彼女らの「読む」には大きな隔たりがあります。
こうした生徒さんの場合、まず悪い癖を抜くことや、「読む」ということへの意識付けから始めないとなりませんが、悪癖が強く固着している場合は、かなりの難事業になります。私どもには色々な「引出し」がありますが、それでも1年ぐらいかかることはザラです。
別に彼・彼女らを責めているわけではありません。むしろ彼・彼女らは被害者でしょう。スマートフォンでYouTubeにアクセスすれば一瞬にして面白い動画が見られ、LINEを使えば即座に他者と繋がれる。生まれた時から極度に高速化した情報社会に暮らしている彼・彼女らにとって、答えや結果は「即座に」得られるもの。
しかし、読解力や国語力を身に付けるのは、その真逆を行く事業です。そこに読解力指導・国語指導の現代的な課題があると思うんですよね。
そして、適切な読解力・言語操作能力を身に付けた人だけが、情報社会の中で適切な情報を取捨選択して、自ら情報を発信できるようになるというのは、現代的な皮肉だと思います。
ちょっと差別的に聞こえるので、今はあまり使われなくなったことわざがあります。「慌てる乞食は貰いが少ない」。急ぎすぎると悪い結果を招くという戒めですが、私が通っていた幼稚園の先生は、よくこの言葉を使って私達園児を大声で怒鳴り倒していました。恫喝といってもいい(笑)。
園児に怒り顔を近づけて大声で「あーわーてーるーこーじーきーはぁ〜!もーらーいーがーすーくーなーいぃ!」とやるんですが、みんなその先生が怖くて怖くて硬直状態、泣き出す子も多数。今だったら絶対に問題になっていると思いますが、この年齢になってみると先生のお言葉には共感あるのみ。
私風に言い換えておくと、「慌てる学びは貰いが少ない」でしょうか。私達は怒鳴りつけずにやんわりと根気よく同じ趣旨のことを伝えております。