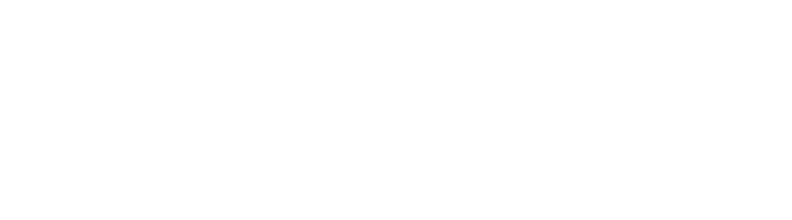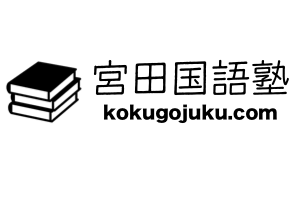受験国語を教えるという仕事柄、色々な入試国語問題に触れるんですが、「興味深い見解」や「思わず深く肯いてしまう主張」を見つけることもしばしば。そうした部分をお裾分けしようというのが、この「入試国語出題文から」というシリーズの趣旨です。難解な文章を平易に解説する、なんてのは授業に任せて、ブログでは、難解な文章は難解なまま、平易な文章は平易なまま、放り出すようにしてご紹介しようと考えています。
さて、初回は、某大学を対象とした模試の問題文から。日野啓三『文体について』です。
かなり硬質な文章ですが、論旨は明確です。ある程度私の方でまとめてみます。
「文体」とは何であるかという自問に対し、日野啓三は下記のような答えを用意します。曰く、
「事物を掴みとっている精神力の強さ」
「雑然たる事物、混沌茫漠たる存在から、何らかの形を抽き出して形づくる能力」
「魂の抽象力」と。
そうなんですよね、目の前に広がる混沌から、真髄とでも呼ぶべき部分を暴力的なまでに抽出する。それを文体と呼ぶかは別として、その抽象力は心に感動を呼び起こす作品の必須条件でしょう。小説であれ、音楽であれ、絵画であれ、ジャンルは問いません。私はこうした事柄を「魂」と呼び習わしているんですけどね。
話はやや逸脱しますが、1960年代頃から、米国黒人音楽が「ソウル・ミュージック」と呼ばれることになったのは故無きことではありません。歌われる題材は極めて卑近な事柄でありながら、そこから抽象される人間の根源に触れるような感情を迸らせる音楽。そうした音楽を人々が「ソウル=魂」と捉えたのはとても自然なことに思えます。この事柄は、日野啓三の言う「文体」「スタイル」とほぼパラレルです。
重要部分を引用します。
実在の混沌と虚無を前にして(内部に感じとってといってもいい)、そこにひとつの形をつくり与える、というより、われ知らずつくり出してしまう人間の不思議な力に対する感動、といってもいいし、何らかの形なしには生きられない人間の根源的不安定さに対する怯えと畏れの感情といってもいいが、そのような底深い感情の震えを誘い出してくれる形。現在、私が「文体がある」と生々しく感じられる作品とはそのようなものだ。
深く深く同意します。私が求めている物語も、音楽も、ライブも、演劇も、そういうものです。
ただ、こうした「感情の震え」は、ぼんやりとしていては味わえません。日野啓三曰く、
それこれの小説に文体があるかないかまで感じとるには、きわめて鋭敏な感覚、良い目と良い耳、いわば芸術的な感受性を必要とするように思われる。
鈍感な私ですが、芸術的感受性を研ぎ澄まし、目を耳を利かせてゆくことは、一生の楽しみであるような気がします。