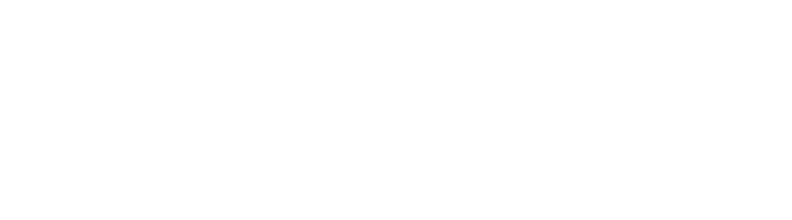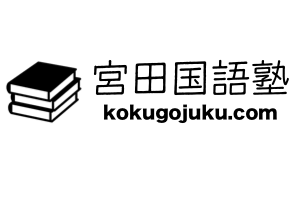ずいぶん長い間ブログを放置してしまいました。そろそろ復帰したいと思います。
現在の私の生活は当然のことながら、塾仕事が中心となっておりますが、身体も鍛えておかねばなりません(自営業は身体が資本なのです)。その二つが私のベースをなす「仕事」なんですが、それと同じぐらい重要なのが「勉強」です。
何と言えばいいのでしょうか、年を重ねるごとに勉強したい事柄は増え、勉強したい気持ちはますます強まります。自分の人生の残り時間を考えて、「あとどれだけのことを学び、どれだけのことを知ることができるんだろう」と思うことが増えてきました。
以前もこのブログに書いたことがあるんですが、私の父は59歳になったばかりで世を去りました。そのせいで、いつもその年齢を基準に物事を考える癖がついてしまっておりまして、その伝で行くと私に残された時間は3年間。
もちろん、その時に死ぬと決まっているわけではありません。むしろ健康診断では、非常に優良な値が出ております(笑)。が、仮にあと三年後に死ぬとしても、それなりに満足できる人生だったな、大きな不満なくこの世を去れるな、という気持ちになりたいと思うんですよね。
私、セネカ(ローマの哲学者)の言葉が大好きなんですが、彼はこんなことを言っています。「人生の短さを嘆く人は多いが、人生は十分に長い。ただし、その使い方を知っている限りにおいて。」
本当にそうだと思います。私の場合、その「使い方」を心から知りたいと思っていて、それが「学問をしたい」という気持ちに繋がっているところがあります。
セネカが暴君ネロに自害を強要されて自らの命を絶った時、実際にどんな気持ちであったかを知る由はありませんが、年齢と彼の言葉を考えると案外納得しながら死を受け入れたのかもしれないなと感じます。
つい最近、組織学習について勉強していたとき、推薦されていた論文に目を通していると、こんな記述がありました。
Since long-run intelligence depends on sustaining a reasonable level of exploration, these tendencies to increase exploitation and reduce exploration make adaptive processes potentially self-destructive.
(James G. March : Exploration And Exploitation In Organizational Learning から引用)
概要を言うと、「長期にわたる知性は「知の拡大」にかかっているのであって、「知の深化」に力点を置きすぎると、組織の適応プロセスを自己破壊的なものにしてしまいかねない」ということなんですが、心から賛同して思わずため息が出ました。
もっと平たく言うと、今知っていることをさらに深めることは楽だし、稼ぎに繋がりやすいけれど、知を貪欲に拡大していかねば、組織としてはいずれ死に至りますよ、という感じでしょうか。
さっきのセネカの言葉が学問の本質的な有用性を物語っているとすれば、こちらの論文は学問のプラグマティックな必要性を伝えてくれているように思います。いずれもが私の心の底に深く訴えかけてくる言葉です。
私たちがお預かりしている生徒さんは小学生なので、上記のような小難しい話をするわけではないんですが(したら訳わからんおっさんだなと思われます)、「勉強することは大事なんだよ」というメッセージを陰に陽に生徒さんたちに伝えるにあたって、ウソがあってはいけないということもまた事実。教える側が本当に「勉強は大事なんだ」と心から信じていることは、結構大切なことだと思っています。
さてさて、学問の話はそれぐらいにして、もう少し言い訳を連ねておきますと(笑)、仕事・運動・勉強以外に、いつもそれ以外のサイド・プロジェクトを抱えている状況になっています。各サイド・プロジェクトは、仕事に関係があるものもないものもありますが、今年2025年度は4つのプロジェクトを完了する予定でいます。
プロジェクト1もプロジェクト2も今年前半で終えるはずだったんですが、スケジュールが押しに押して、このお盆休暇中にようやく両プロジェクトを完了した次第。塾が休みに入ってからひたすらその作業をやっていまして、実際上あんまり休みじゃなかったんですけれど、まあしようがないですね(笑)。
お盆開けからはプロジェクト3・4に着手して今年中に完遂できればいいんですが、何かまた時間がかかりそうな予感が……。塾仕事と直結するプロジェクトでもあるので、頑張っていきたいと思います。
といこうことで、お目汚しブログですが、またちょこちょこと更新したいと思います。宜しくお願い申し上げます。