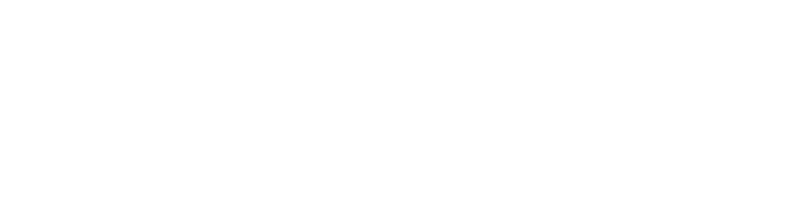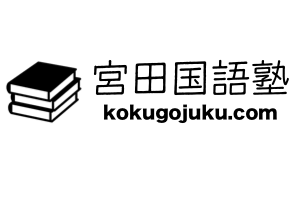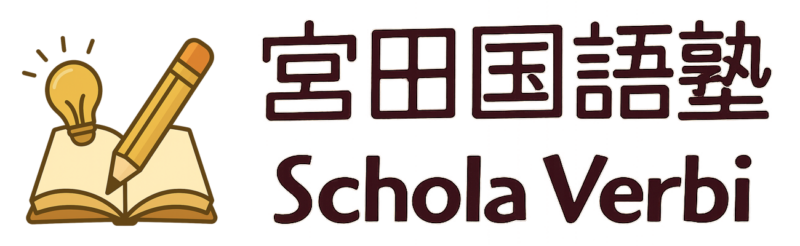ロベルト・コトロネーオ(Roberto Cotroneo)の『ショパン 炎のバラード』(原題:Presto Con Fuoco) について。
この本、購入したのはずいぶん前。発売直後でした。今調べてみると、2010年に発売ですから、もう5年近く前の話ですね。
ゆっくり本を読む時間がなかなか取れない生活をしているので、裁断・スキャンした後でiPhoneやiPadを用いて読む、または、裁断後の書籍を風呂場で読むというのが主な読書方法になっています。
で、この『Presto Con Fuoco』、表紙が美しいんですよね。私はショパンの大ファンなので、伝記等をあれやこれやと読んできましたが、こんなにショパンを体現した表紙も珍しい。知的で繊細で雄々しくてすっきりしていて。
ショパンのファンなら、この肖像画を描いた画家もすぐに分かりますよね。そう、ショパンの友人、ウジェーヌ・ドラクロワです。しかも、ショパンの絶筆がうっすらと見えるデザインとあっては、なかなか裁断する気になれず、今まで書架の肥やしとなってしまっていたのでした。
結局、古本をもう一度買い求め、裁断した上でiPadで読んだり、入浴時に読んだりしたのがつい先頃の話。どんな新本でも平気で裁断する私には珍しいパターンの行動です。
何と言いますか、好きな人にとってはとにかく扇情的な文句が帯に踊っています。かのウンベルト・エーコが激賞したとか、ショパンには知られざるバラード4番の未発表楽譜があるとか。もうこれだけで、ショパン好きなら絶対に読もうと思いますよ。
極めつけは、こんな推薦文。
ショパンのバラードの第四番は天下の名曲だが、この本はそれをめぐって、磨ぎすまされた推理と秘められた情熱が織りなす物語である。これに肩を並べるものといえば、私にはウンベルト・エーコの『薔薇の名前』かミケランジェリのピアノ独奏ぐらいしか思い当たらない。
誰が書かれたと思います?実は吉田秀和氏なのです。ああ、もうこれは読まないとしようがない(笑)。
で、感想。全体的な観点から申し上げますと、ちょっと肩すかしの感が否めない小説でした。というか、私の期待が大きすぎたという方が正確なんでしょうね……。面白かったか否かと問われれば、極めて面白かったと断言できますが、バラード4番の知られざる最終部分が(楽理に無知な私には)聞こえてこないのが少し寂しい。
「小説」だから「聞こえない」のは当たり前ですが、ショパンの絶筆となった直筆楽譜を手にした老ピアニストに、何か劇的な変化があっても良かったのではないかと思ってしまいます。ベタな展開ですけどね。でも、ショパンのバラードにまつわる物語なんだから、ドラマティック過ぎるぐらいにドラマティックでもいいんじゃないか。
むしろ、友人の直筆楽譜蒐集家の方が、世界を揺るがす直筆楽譜にガクガクブルブルしていて共感を覚えてしまいました。多分、私のようなベタな展開を求める読者のために蒐集家というキャラクターが用意されているんでしょうね。
順序が逆になりましたが、あらすじをば。
ショパンのバラード第四番には知られざる遺稿があった。その遺稿楽譜には、現在知られているフィナーレ部分とは異なるフィナーレが記されている。亡くなる間際の衰弱しきったショパンが書いたと思しきそのフィナーレの楽想記号は、「Presto Con Fuoco (情熱の炎をこめて迅速に)」。しかもその楽譜は、愛人の娘ソランジュに捧げられていた……。
楽譜はナチス統治下ベルリン→スターリン支配下モスクワ→サンティアゴと流れてゆき、亡命ロシア人の手によって、パリに住まう極めて高名な老ピアニストへと渡る。ピアニストが読み解く楽譜に秘められた驚異……。
って、書いているだけでワクワクするストーリーです。でも、文章にはかなり癖があり、読み解くには少々骨が折れます。原文がそうなんでしょうが、やや衒学的なきらいがあると申しますか。楽譜を手にするピアニストの主観を巡り続ける構成は、音楽好き・ショパン好きでないとかなり辛いところがあるかも知れません。
ただ、あなたがショパンのファンというなら、エピソードを拾い読みするだけでも、とても面白いはず。
まず老ピアニストはアルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリという設定。私は、読んでいる間中ずっと、あの気むずかしいミケランジェリの顔を思い浮かべていました。多分、作者もそれを期待しているんだと思います。
ピアニスト関連のエピソードをいくつか引用してみましょう。本当か嘘かは知りませんが、とてもリアルで興味をそそられます。
まず、アシュケナージ。うん、若い頃の彼って、カモシカみたいに走りそうな感じがする(笑)。
先日、ここから遠くないところで、ウラディミール・アシュケナージに会った。彼のことはよく知らない。(中略) 銀色の長い髪をなびかせながら、微笑みを浮かべて、私のほうへ走ってきたので、恐ろしくなって、私は針鼠のように後退ってしまった。
ホロヴィッツ。結構ボロクソ。
ホロヴィッツの弾き方が上手でない、とわかったから。あまりにも速すぎる。彼の技法の卓抜さ、極限のヴィルトゥオーゾは、私を苛立たせた。いくつかのパッセージでは、正確さの欠如が、気になった。時間が足りないかのようにして終った。
グレン・グールド。私が(というより世界が)最も愛するピアニスト。
録音をしながら、小声で歌いつづけるグールドのことを、私は思い出していた。彼のレコードのなかでは、バッハの音符の下に、彼の声が聞こえてくる。そして誰もが、彼を奇人のように思いこんだが、そこに自分がいないことの物狂おしい恐怖を、誰もが理解しなかったからだ。(中略) 聴く者に対して、彼が存在していたことを、彼がそこにいたことを、その音楽がグレン・グールドと呼ばれる人物から出てきたことを、(中略) レコード盤のなかにいることを思い出させるための、それは、ひとつの方法だったのである。
ファンの方はよくご存知でしょうが、グールドの録音を聴いていると、ピアノの音に混じって彼のハミングが聞こえてくることがあります。「ン〜ン〜ン〜」「フンフフ〜ン」みたいな感じ。録音エンジニアにいくら注意されても止めなかったらしい。
私はその声が死ぬほど大好きです。というか、それが聴きたくてボリュームを上げてしまう。バッハを演奏して思わず口ずさむのがいけないなんて誰が決めた、演奏者は大いに歌え。そんなことを実行するのは、後にも先にもグールドだけですが、コトロネーオの上記解釈は正しいと思います。
最後にミケランジェリ(らしきピアニスト)がショパンについて語る一節から引用したいと思います。そうなんだ、そうなんだ、正にそうなんだ。私もそれが言いたかった!
筆者コトロネーオは音楽教育を受けた人で、ピアノも巧みらしい。音楽に対する理解力が、私とは比べものにならないぐらい高い人だと思いますが、その人が(おそらくは自分の意見として)こう書いてくれているのはとても感動的です。
こうして私が出会う婦人たちは、たとえば、ワーグナーのすべてを知っているというふりをしたり、いかにも慇懃に私に尋ねたりするのであった。どのようにして私が、ほとんど生涯をかけて、フレデリック・ショパンのような作曲家の、演奏やら、解読に、没頭したのか。あの気障な、ロマン主義の、マイナーな作曲家は、一生のうちに交響曲の一作も、オペラの作品一つも、書きあげなかったのに、と。それゆえ私は、黙って、相手の目を見つめ返し、答えるべき言葉を失うのである。そして心のなかで、繰り返すのであった。あなたは、考えたことがあるのか、この世に神が存在するかどうかを。もしも存在したならば、ひとつの音だけでも、出したことがあるだろうか。この愚かなる人びとの住む、宇宙のなかで、見分けるのが困難な、単なる叫び声とはちがう、ひとつの音を。
この部分を読むだけでも価値あり。
誰にでもお薦めの小説というわけではありませんが、ショパンまたはミケランジェリのファンなら、読んでおいて損のない作品です。