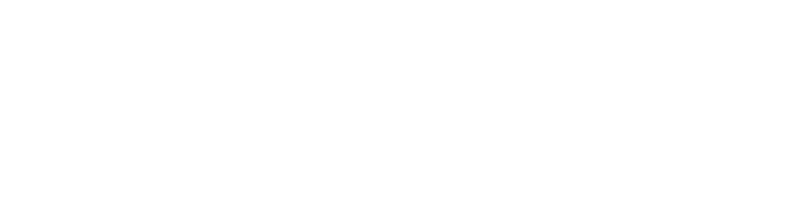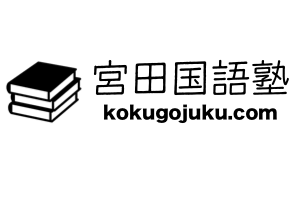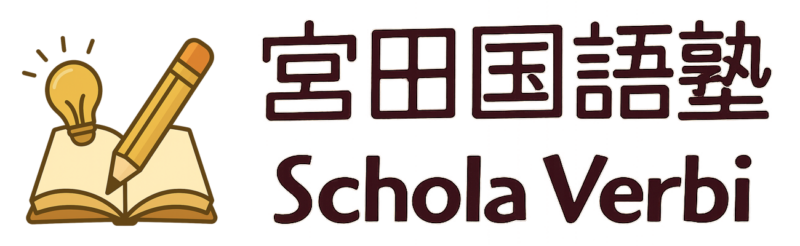これは是非当ブログに書いておくべきだと思う新聞記事に出会いました。
現代国語の正解とは?小川洋子が挑む自作小説の入試問題
朝日新聞デジタル 2021年7月11日 10時00分 太田啓之執筆
(以下、「朝日新聞記事」と略します。)
現代国語の入試、特に読み手によって抱くイメージが異なる小説の入試問題には、万人が納得する「正解」があるのか。公正な採点は可能なのか。疑問を感じたことのある受験生や元受験生は少なくないでしょう。
そこで、ベストセラー「博士の愛した数式」などで知られる作家の小川洋子さんに、自作の長編「ことり」から出題された東北大の入試問題(2019年度前期「国語」)を解いてもらい、「小説の入試問題の正解とは何か」について考えていただきました。
(「朝日新聞記事」より引用)
これは素晴らしい着眼点です。
以前から、「筆者自身が自分の書いた文章に基づく入試国語問題を解くとどうなるのか」という話はありまして、実際、超頻出随筆家であった小林秀雄が自分の文章に関する入試問題を解いたというエピソードが有名です。小林秀雄の娘さんが国語の勉強をしていて、自分の父親の文章を使った問題に出会う。父親に実際に解いてもらうと、模範解答とは似ても似つかぬ解答になる。「こんなこと筆者は一つも考えとらん!」と、小林秀雄は入試問題や模範解答に対し激怒したとか(笑)。
そうなんですよね、入試国語では「筆者の考え」そのものが聞かれているのではありません。それはその筆者自身にしか分かり得ないわけですから。
聞かれているのは、「標準的な読者が読み取るであろう『筆者の考え』」、さらに言えば、「知的階層に属する者が読み取ると考えられる『筆者の考え』」です。もっと有り体に言えば、「出題者の考える『筆者の考え』」ですね。
頭の良すぎる人は、その頭の良さ故に、そこを勘違いしてしまうことがあります。「入試問題」はあくまでも「入試問題」なのであって、文学研究ではありません。真の「筆者の考え」が問われているのではないと理解して、合理的に勉強を進めて欲しいと思います。
閑話休題。この企画に協力してくださっているのは小川洋子氏。彼女が素晴らしい筆力の持ち主で、今の日本を代表する小説家であることに異論のある人はまずいないでしょう。今までこのブログでも彼女の作品については何度か取り上げたことがあります。
ここは私見ですが、彼女の文章からは、物事に真摯に向き合う誠実さのようなものをいつも感じます。私も妻も、そこにアーティストとしての魅力だけではなく、人間的な魅力を感じているのだと思います。
こんな名実ともに超一流の小説家を、現代国語の入試問題の世界に連れてきてくれた朝日新聞、それから勿論のことですが小川洋子氏ご本人にも大いに感謝して、記事を見ていきましょう。
まず入試問題の素材になっているのは『ことり』という小説。入試問題は、東北大学2019年度前期の国語問題です。堂々たる旧帝大の入試問題、相手にとって不足はありません。
東北大学の入試問題は、下記リンクからご覧になれます。とても味わい深い文章ですし、記事の理解のためにもご一読いただければと存じます。
いかがでしたでしょうか。問題としては、標準的な難易度だと言えるでしょう。超難問というわけでもなく、かといって超易問というわけでもありません。
正直に書きますが、現在の難関中学入試の国語問題のレベルもこれぐらいです。大学入試の国語問題が易化しているのではありません。中学入試の国語問題が難化しているんですね。この問題も「狼狽」の意味さえ伝えておけば、十分に中学入試の指導教材として使えると思います。
そんなわけで、この記事は中学入試・大学入試両方向けの記事だとお考えいただければ幸いです。
それでは、一番重要だと思われる問題5を見てみましょう。
主人公である「小父さん」には、鳥のさえずるような言葉を操る兄がいました。その言葉を理解できるのは「小父さん」だけ。「小父さん」は兄を失って以来、図書館に通って「鳥に関する本」を借りては読んでいます。鳥そのものを取り上げた本でなくとも、少しでも鳥に関係があれば片っ端から読みつつひっそりと暮らす毎日。そんなある日、若い女性の司書から突然「いつも、小鳥の本ばかり、お借りになるんですね」と声をかけられます。
「小父さん」は狼狽(ろうばい)しますが、司書は楽しげに彼に話し続けます。どう反応すればいいかわからない「小父さん」。図書館からの帰り道、小鳥の絵が描かれていたキャンディ「ポーポー」を買うために兄と通った「青空薬局」の前を通り、「ポーポー」の不在から「小父さん」は兄の死を実感します。
その後に続く文章は次の通り。
「返却は二週間後です」
ペダルを踏む足に力を込め、もう一度繰り返した。本の立てる音と風の音に自分の声が紛れ、代わりに司書の声が耳元でよみがえってくるのを小父さんは感じた。彼女の声をもっとよく聞きたくて、更に力一杯ペダルを踏んだ。(小川洋子『ことり』より引用)
問五
傍線の箇所(エ)「彼女の声をもっとよく聞きたくて、更に力一杯ペダルを踏んだ」には、「小父さん」のどのような気持ちが表れているか、「小父さん」の心情の変化に着目して七十五字以内で説明せよ。(東北大学2019年度前期・国語問題より引用)
小川さんの答えは「たった1人、鳥の本を読み続けていた自分に目を留めてくれる人がいたと気づき、そのことに動揺しつつも、司書に対して親しみの情の芽生えを感じている」。
東進の解答例は「兄の死後、小鳥の本に没頭し、他者との交流が希薄な日々を送っていたが、一応心の整理がつき、司書との交流を楽しみにする前向きな気持ちになっている」。
(「朝日新聞記事」より引用)
皆さんの解答はどうでしたでしょうか?
小川洋子氏の解答はすごく素直でいいなと思いました。ストレートな説明で入試問題から離れて考えれば、バッチリ正解です。というか、作者に対して「正解」も何もあったもんじゃないですけどね。失礼極まりない物言いであることは重々承知いたしておりますが、入試国語の解説記事としてご了承下されば幸いです。
一方、入試問題の解答としては、東進解答例の方がよいでしょう(もちろん、あくまでも入試問題解答としての評価です)。
問題文をよく見てみましょう。「『小父さん』の心情の変化に着目して」とありますね。これは入試問題としては、「変化前の心情」と「変化後の心情」両者の説明を求められていると考えるべきです。
したがって、
変化前の心情:他者との交流を進んで求めようとはしない消極的な気持ち
変化後の心情:女性司書との交流を楽しみにする積極的な気持ち
の両者を「はっきりと」つまり「採点者にわかるように明示的に」示してやるのがよいと言えます。その意味で東進の解答例は優れています。
加えて、その心情の変化を促した契機「ポーポーの不在→兄の死の実感と受容」も、「一応心の整理がつき」というように(苦しいながらも)触れられています。評価の高い解答になるでしょう。もう少し制限字数を増やして欲しい気はしますが、これは東北大学の出題者への文句になってしまいますね(笑)。
一方、小川洋子氏の解答は、変化後の心情に着目しています。分解するとこんな感じ。
1.自分に目を留めてくれる人がいることへの気づき
2.動揺
3.司書に対する親しみの情の芽生え
「変化後の心情」に字数を費やしている分、より深くその心情が描かれていますが(さすが小説家だと思う)、採点では先程述べたようなポイント、つまり「変化前の心情」「変化後の心情」「契機」に触れられているかが重視されるであろうと思います。
強いて言えば「気づき」という表現には、「気づく前」と「気づいた後」をイメージさせる力がありますし、「芽生え」も「芽生える前」と「芽生えた後」を含意する表現ですが、そこを採点者がどう評価してくれるかですね。おそらく、そこまで善意解釈はしてくれないのではないかと。
あと、「更に力一杯ペダルを踏んだ」という表現に見合う「積極性」「前向きさ」への言及も出題者は求めているでしょうから、その意味でも「入試国語の解答としては」改善の余地ありということになります。
ただ、彼女は受験生でありません(当たり前ですが)。受験のような小さな世界ではなく、文学の世界で羽ばたき続ける人です。「入試問題で小説を取り上げることの意義」を丁寧に語ってくださっていることに感謝すべきだと思います。
小川洋子氏のお言葉をいくつか引用してみましょう。
小川さんは「解いてみて、小説にとって本当に大事な登場人物たちの心の動きを、自分が直接書いていないことを思い知らされました。小説はそれでいいし、読者も『何となく感じる』だけでも構わないけれど、入試問題はあえてそこを聞いてくる。輪郭がぼやけているものに、しっかり言葉をあてはめてみることは、作品のより深い理解にもつながります。国語を勉強する上で絶対に無駄ではない」と話す。
(「朝日新聞記事」より引用)
「輪郭がぼやけているものに、しっかり言葉をあてはめる。」それはとても大変な作業なんですが、これこそが言葉を扱う上で重要なトレーニングなんですよね。論説文などでは論旨がクリアに提示される分、そうした力は養いにくいと言えます。表現しにくい何かに言葉を与えて輪郭づけられること。それはとても大切な能力です。この点に関しては、こんな風にもおっしゃっています。
論説文のように事実やロジックを伝える文章ではなく、読む人によって印象が異なるであろう小説を、入試問題に取り上げることをどう考えますか。
「不都合はないと思います。ロジックを勉強するのは、数学や物理でできるけれど、そこからはみ出してしまうものにも、大事なことがたくさんある。それを扱うのが小説です。いったい何を言っているのかよく分からないし、問題を解こうとしても、正解の手応えがなかなか得られない。そんな曖昧(あいまい)さに耐えつつ、答えとして何かを絞り出す。言葉に対する信頼や執念を問うのが、小説の入試問題なのでしょう」
(「朝日新聞記事」より引用)
ロジック崇拝とでもいうべき風潮が強まっているような気がします。これ、教育現場では「理系科目重視」という形で現われる、逆に言えば「文系科目軽視」ということになるんですけれども(笑)、やはりそれでは十全な教育とは言えないでしょう。
個人的には、論理の枠からこぼれ落ちるものも軽視しないで欲しいんですよね。その際の手応えの無さや曖昧さに耐えて欲しい。そして「言葉に対する信頼や執念」を持ち続けて欲しい。そんな風に考えながら日々生徒さんに向かっています(ちょっと大げさですけれど)。
「小説の言葉は、電子メールやラインの言葉とは全然違う。文学の独特な言葉と戯れることで、言葉の本質への感覚が研ぎ澄まされます。それは現代文や古文の問題を解いたり、論理的な文章を読み込んだりするのにも、絶対役立ちます」
(「朝日新聞記事」より引用)
受験生にはこの小川洋子氏の言葉を胸に刻んで欲しいですね。
小説も論理的な文章も言葉。古文も漢文も言葉。英語などの諸外国語も言葉。もっと言えば、数学も数的な言葉。物理学も物理的な言葉。私から言わせてもらえば、すべての学び・研究は「言葉」に基づいています。それを疎かにしてどうする、それを鍛えないでどうする。
そして私がこのブログ記事で一番伝えたい、小川洋子氏の言葉。
「それに、小説を読むことは、突き詰めれば『他者をどれだけ思いやれるか』につながる。社会生活を営む上でも重要な能力です」
(「朝日新聞記事」より引用)
本当にその通りだと思います。自分とは異なる立場や境遇の人々への思いやり。それこそが小説を読むことの出発点であり、ゴールでもあると思います。各中学や大学がそうした「他者を思いやる力」を求めないはずがないですよね。そしてそれは小川洋子氏がおっしゃる通り、「社会生活を営む上での重要な能力」でもあります。家族の一員としても、学校の一員としても、会社の一員としても、それはこの上もなく重要な力。
実際、わがままに育った子どもは国語(特に物語・小説)の成績が明らかに悪い傾向があるんですが、これは小説の読解が「他者を思いやる力」を必要としていることを証明していると思います。
文学と入試問題が触れ合う、そんな素晴らしい企画に感謝します。受験生のみなさん、小説問題を解く時は「真剣に他者の立場に立つ」ということを念頭に置いてくださいね。