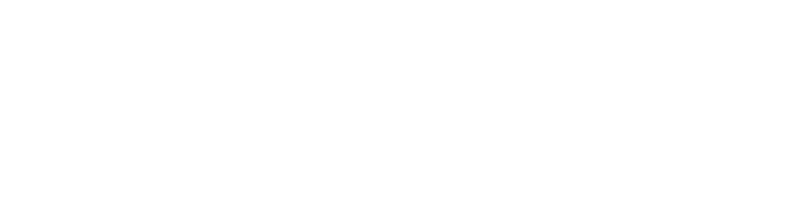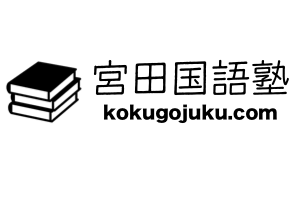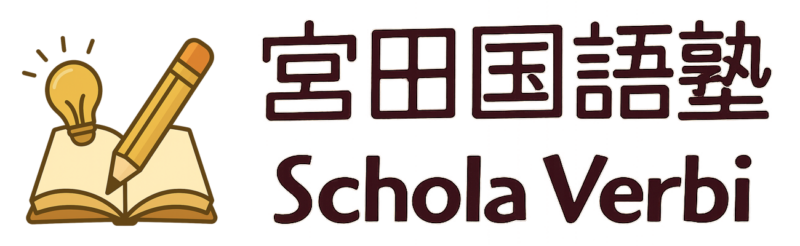クリスマスですね。先日、業務用の日報に日付を書き込む際に、今日はイブだったんだ!と気付いた次第。
ここしばらく朝から晩まで仕事に追われていて、外出することもままならない状況でしたので(出かけるのは深夜のプールだけ)、街のクリスマスムードに気付きませんでした。平穏な心でいられたので、ある意味よかったのかも。
昨年の今頃、妻と絵画展に行ったことを思い出します。私がどうしても見たかった展覧会が伊丹市立美術館で開催されたんです。
その画家は鴨居玲。
絵画に疎い私ですが、何かこの人の絵には惹きつけられるものがあります。最初に彼のことを知ったのは司馬遼太郎のエッセイ。なんと字面の格好良い名前だろうか、もし自分で自分に名前が付けられるなら、こんな名前にしてみたいと思ったことを覚えています。知的で繊細でスタイリッシュな人物像を勝手に想像していました。
絵画にそれほど興味のない私は、そのまま彼のことを記憶の片隅に眠らせていたんですが、妻と神戸に遊びに行った際に、とある場所で気になる絵画を見かけました。説明出来ないけれど何か惹きつけられるものがある。そばにあったキャプションを見て驚きました。鴨居玲の絵だったんです。
それ以来、ずっと彼の絵のことが気になっていたんですが、まとめて鑑賞する機会はないままでした。そして2015年の冬。ようやく彼の絵をまとめて見る機会が訪れました。
それが先述の伊丹市立美術館で行われた展覧会「没後30年 鴨居 玲展 踊り候え」。

「踊り候え」いい言葉です。本当に。
彼の著書のタイトルでもあったはずなので、おそらくは彼自身が好んでいた言葉であったろうと思います。室町時代の『閑吟集』の一節なんですけれど、完全に私と好みが一致しています(画才は何万光年もの隔たりがありますが)。閑吟集は私の大好きな、というか偏愛している作品。「一期は夢よただ狂へ」これ以上の人生の真実があろうか。
彼の画風はどちらかというと陰鬱なものですが、洒落好みで享楽的な彼の人生を考えると、どこか閑吟集と通ずるところがあるように思うんですよね。俳優かと思われるぐらい男前で人の目を惹く存在。会う人が皆たらし込まれるぐらいの魅力的な人物。そうしたところも閑吟集を彷彿とさせる。あっさりと自死を選ぶ恬淡としたところも、そうかもしれません。
絵画の専門的な知識は持ち合わせていませんので、技術論は他にお任せしたいと思いますが、彼の絵には濃密な迫力があります。死の影が濃密である分、生の光の照射が感じられる。
分かりにくいですね。言い換えましょう。自死の数年前に描かれた自画像と思われる男の絵なんかは、魂が口から抜け出ていくのが見えそうなんです。効果音を付けるなら「ほうっ……」という感じ。魂が抜け出るということは、肉体という枠に魂が入っていたということですよね。魂があるからこそ死はあるのだし、死があるからこそ生は輝く。
展覧会の資料から鴨居玲の紹介文を引用しておきます。とてもコンパクトに彼の人生がまとめられています。
兵庫県ゆかりの洋画家、鴨居 玲(1928‐1985)は金沢市に生まれ、金沢美術工芸専門学校(現・金沢工芸大学)で宮本三郎に師事し頭角をあらわします。その後、制作の苦悩を打開するために南米、パリ、ローマを旅することで作品を劇的に深化させ、安井賞をはじめ輝かしい受賞歴を得ますが、日本に安住することなく再びパリ・スペインで研鑽を積みました。特にスペイン、ラ・マンチャ地方で交流した村の人々の姿に自己を投影した作品群は、人間の内面を鋭く抉り出し、見る者を圧倒する迫力に満ちています。そして、渡欧前および帰国後は阪神間に画室を持ち、同地で没するまで、人間の本質的な部分である、孤独、不安、運命、愛に正面から対峙することで独自の崇高な芸術世界を築き上げました。その自己追及の苦悩から生み出された深く暗い色調の画面には、見る者を強く鼓舞してくれる、生きることへの光明が見出され、没後30年を迎える今なお、多くの人々を惹きつけ魅了する力に満ちています。
彼の実際に使用していたイーゼルや画材も置かれていたんですが、凄まじいものでした。下の絵にも見えるイーゼルです。画家魂というか、表現者魂というか、とにかく荒ぶる魂が未だそこに彫りつけられている。

これは亡くなる数年前の自画像。とても大きな絵でした。半開きの口と、太ももに挟んだ両の掌と。堪らない。
この数年後、鴨居玲は自死を遂げるんですが、その絶筆の襖絵がまた凄まじいものです(これは展示されていませんでした)。自死の当日に猛烈な速度で描いたと思しき絵は、自らの縊死体と生首。ほとんどの方が一度見ると忘れられないだろうと思います。インパクトがありすぎるので、あえて当ブログには載せません。
昨年の今頃は、妻と鴨居玲の話ばかりしていました。矛盾に満ちていて、それだからこそ魅力的な彼の絵と人生。これからも多くの人を魅惑することは間違いないと思います。