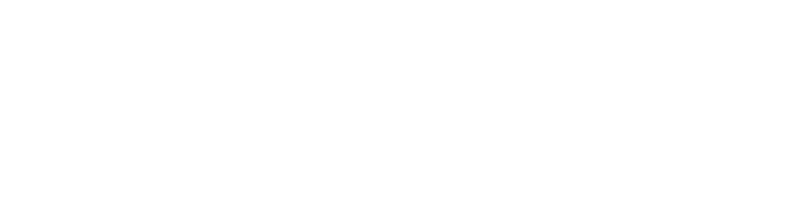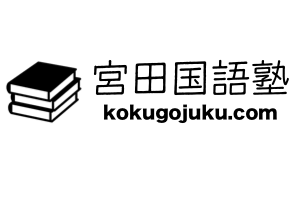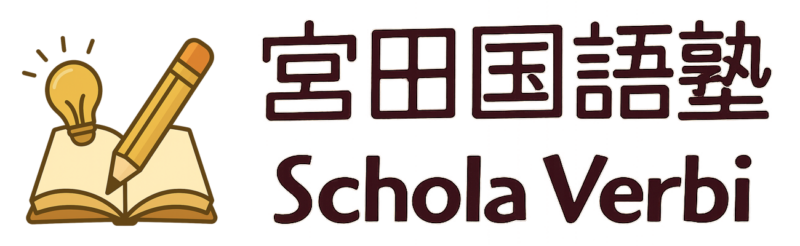下記の記事を書いた後、今まで触れてこなかった「マジック・リアリズム」を少し勉強しておこうと思い、ガルシア・マルケスの小説『エレンディラ』を読んでみました。
授業補助資料 – 京大入試2010年国語問題 津島祐子『物語る声を求めて』:国語塾・宮田塾のブログ
「マジック・リアリズム」とは、ラテンアメリカ文学における魔術的リアリズムを指すんですが、今まで該当作品を読んだことがなかったんですよね。
いや、面白いのなんの。私の後に妻も読んだんですが、二人ともお気に入りの作品となりました。
この『エレンディラ』、短編集なんですけれども、各短篇に登場する人物が微妙に重なっており、一つの世界をなしています。細密なエピソードを丁寧に重ね、読者の前に風景を浮かべるような作風は、かなり映像的なセンスを感じます。
私が思い出したのは、アレハンドロ・ホドロフスキーの映像作品。高校生の頃見た『ホーリー・マウンテン』のような、不可解かつグロテスクかつ性的かつ血みどろな映像に近い味わい(?)があります。この映画、中高生には到底お勧めできませんが、一般の大人にもお勧めできません(笑)。あまりに毒々しいので、アンダーグラウンド文化に理解にある方限定で推薦。
さて、マルケスの作品も、どこかしら南米らしい血や性や死の匂いが漂っています。しかし、それが生々しいわけではなく、どこか「乾いて」います。例えば、祖母に少女の頃から娼婦として生きることを強いられるというエレンディラも、とても悲惨な人生を送っているんですが、どこか飄々としていて、ウェットな感情が入り込む余地がない。あまり知的でない女性であるけれど、人生を達観しているというか。男や家族に粘着的にこだわることなく、荒野に駆け出しそうな女性です(実際にそういうシーンがある)。
死や死者もふんだんに取り扱われますが、そこにもウェットな悲しみはありません。死がごく当然の終着点であるかのように取り扱われます。死体は汚れた寒い海へと放棄され、誰も顧みることがない。
何なんでしょうか、この乾いた雰囲気は。とても魅力的です。
といって、物語性までもが乾いているわけではありません。むしろ、濃密な物語性に充ちあふれています。ガルシア・マルケスは幼い頃、祖母と暮らしていたそうで、その祖母から、夢ともうつつともつかぬような伝承・民話・噂話をずっと聞き続けていたとのことなんですが、ラテンアメリカ的な物語性と、美しく乾いた不条理性はそこで培われたに相違ありません。
話としての興味深さは、タイトルだけでもある程度伝わるんじゃないでしょうか。いくつか列挙してみます。
「大きな翼のある、ひどく年取った男」
「この世でいちばん美しい水死人」
「無垢なエレンディラと無情な祖母の信じがたい悲惨の物語」
どんな話か気になりますよね。どの物語も、ガルシア・マルケスの向こう側にいるお婆さんから「昔こんな事があったんじゃぞ」と聞かされているような気になります。そして、その物語はどれも微妙に歪んでいます。「魔術的」と呼ばれる所以はそこにあるんでしょう。例えば、上記「この世でいちばん美しい水死人」ですと、こんな感じです。
海を漂ってくる黒い漂流物。見つけた子供らが海藻などを取り除いてみると水死体だったという話の後、こう続きます。
「子供たちは午後のあいだ水死体を砂に埋めたり、掘り起こしたりして遊んでいたが」
ええっ、水死体って遊び道具になるのか?疑問に思いながら、大人達が水死体を村の家に運び込むシーンを読んでみると、
「地面に横たえてみると、体が図抜けて大きく、とても家に入りそうになかった。水死体のなかには死後もどんどん成長するものがいるが、きっと、あの男もそうにちがいなかった。」
ええっ、水死体って成長するのか?更に読み進むと、
「あの水死人は海の溺死体のようにさみしそうな顔をしてはいなかったし、川で溺れた人間のように卑しくさもしい表情を浮かべてもいなかった。」
ええっ、水死体って海か川かで表情が変わるのか?
とまぁ、全編こんな感じで物語が進んでゆきます。最初は疑問に思いながらも、その話術に楽しく乗せられてしまう。これこそ「物語」の醍醐味です。
調べてみると、ノーベル文学賞を獲得した『百年の孤独』は、これに輪をかけたような作品とのこと。またいずれ、そちらも読んでみたいと思います。