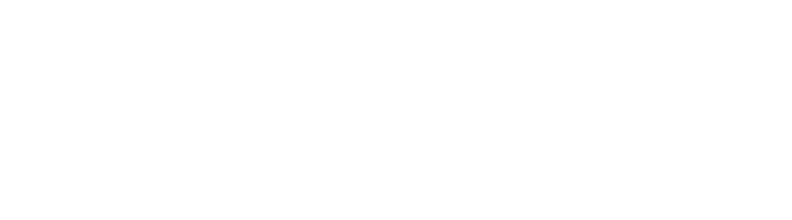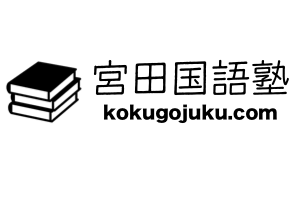先日、出先でテレビが流れているのを見ていると、とある歌手がご高齢の方々の前で古い歌謡曲を歌っていました。『高校三年生』。舟木一夫の、いわゆる青春歌謡とでも呼ぶべき歌です。
さすがにリアルタイムで聴いてきた歌ではありませんので、個人的な感慨はありませんが、ご高齢の皆さんは、嬉しそうに手拍子を打ったり、一緒に口ずさんだり。ご高齢の方々からすると、郷愁を誘う歌なんでしょうね。
で、思ったんですが、どうして「高校三年生」なのか。ご高齢の方々が過ぎ去りし日々を思い出すというなら、別に「小学六年生」でも、「中学二年生」でも、「社会人一年生」でも、「新婚一年生」でもいいんじゃないのか。
いや、それは屁理屈であって、やっぱり「高校三年生」が一番しっくり来る気はしますよね。じゃあ、それはなぜなのか。
思うに、「高校三年生」が追憶して感傷に浸るに最もふさわしい時期であるというのは、この年齢が「何かを捨て去る時期」にあたっているからなんだと思うんですよね。
小学生や中学生は、まだ何かを捨て去る時期ではありません。庇護者のもと、何かを得たり身に付けたりする一方の時期。勉強であれ、人間関係であれ、何かを捨て去るという実感を持つ子どもは少ないでしょう。
逆に、大学生や社会人は、何かを捨て去る経験をいくつか経験してきているはず。大学で法学を専門的に学ぶことにしたなら、普通は医学や哲学を「捨てる」ことになりますし、社会人になる際は、大学での勉学を選択しない、もしくは、大学での勉学を終えるというふうに、何かを「捨てる」経験をしてきたはず。
上記の時期のまさに狭間にある「高校三年生」は、子どもであることが許されてきた時期を捨てさせられる、つまり、人生というステージにおいて初めて何らかの選択を強要され、捨てないことが許されなくなる時期なんだと思うんですよね。
とすれば、人生も終盤にさしかかかって、来し方を振り返ると、その時期が最も「喪失感」に満ちたものに見え、その切なさ故にこそ、輝かしく見えるのではないか。それより前の時期や後の時期は、「喪失」を知らなかったり知りすぎていたりで、感動を呼び起こしにくい。
実際、歌詞をよく読んでみると、次のような事柄が提示されています。「夕日が赤く染める校舎(上る朝日が染めるのではなく、沈み行く夕日が染めていることに注目)」「思いを寄せる女性」「クラスの仲間」。いずれも、卒業を機に捨て去らねばならないものばかりです。
そうそう、この曲のメロディって、いかにも遠藤実らしい和風の短調ですが、これも「喪失感」を増幅させるのに役立っているでしょうね。
舟木一夫/高校三年生
個人的には、「高校三年生」というと、つい最近という感じがありまして(厚かましすぎ(笑))、あんまり郷愁は覚えません。
少し文句を変えて、「高校八年生」と歌ってみると、趣が変わってよろしいんじゃないでしょうか。「もう後がない!」「いい加減卒業しろよ!」みたいな。
高校を卒業してずいぶん経った者の戯れ言でございました。