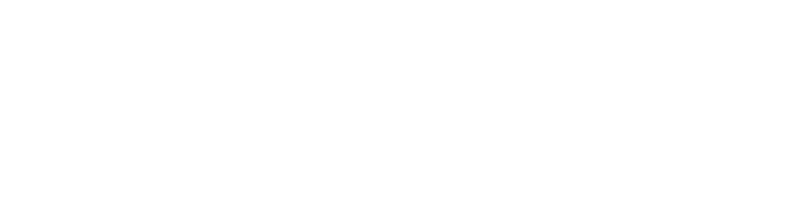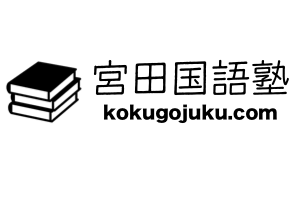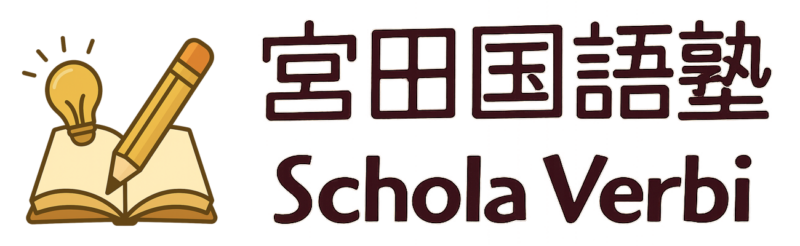最近読んだ日高敏隆先生の本の話です。日高先生のお書きになった文章は、中学入試から大学入試に至るまで、あらゆる入試の素材になっています。取り扱っている生物学的な題材が面白いですし、理系っぽい理屈臭さがないところも好まれる所以でしょう。特に灘中なんかは複数回利用しているはず。
そんな入試業界で人気のある日高先生の著書を久々に読んでみました。『動物と人間の世界認識』(筑摩書房)です。
動物と人間の世界認識―イリュージョンなしに世界は見えない
日高敏隆

アマゾンをうろうろして書籍レビューを読むのが好きなんですが、良いレビューがあるとついつい読みたくなってしまうんですよね。最近は中古の安い本まで入手できるようになっていて、とても便利。加えて、iPhoneやiPadから本当に簡単に購入できるので、ついポンポンと買ってしまいます。『動物と人間の世界認識』もその流れによる購入です。
原則として、下らないと思った本はこのブログで取り上げていませんから、この本もお薦めできる本です。ただ、冗長性はやや高い(同じテーマが繰り返される)。専門書でなく一般人向きの書である以上、私はそれを悪いことだとは思いません。
繰り返されるテーマは、「どんな動物もイリュージョン(幻想)のもとに生きている」ということ。ネコはネコのイリュージョンを抱えて生きており、モンシロチョウはモンシロチョウのイリュージョンに包まれて生きている。もちろん、人間も然り。
ユクスキュルという学者の提唱した「環世界論」という概念を敷衍したような書物なんですが、そこは日高先生、面白い例を引っ張ってきて読者を楽しませてくれます。
それは、昔の日本人が「生き物」をどう捉えていたかという話です。昔の日本人は、どのようなイリュージョンをもって生物を見ていたのか。もちろん、その調査対象は「古典文学」ということになります。
何でも、日高先生は「古典学の再構築」という文部科学省の科学研究費による研究グループに加わられて、『万葉集』などをお読みになったとのこと。生物学者が万葉集を読むとどう感じるのか、今まさに万葉集を読み進めている私(なかなか進まないんですが全編の4分の1ぐらいは読みました)からすると、とても興味深い話です。
約4500首を収録する万葉集には、合計100近い動物名が出てくるので、これら多数の動物の歌を分析すれば、万葉時代の動物相が判明するのではないかというのが当初の先生のお考え。
が、しかし。事態は全く異なりました。
ここからは面白い部分を引用してみましょう。
哺乳類のひとつとして、イサナすなわちクジラが出てくる。しかし、このイサナが登場する歌を順番に見ていくと、クジラの現実の姿をあらわしたものはひとつもない。狩る様子を述べた歌もない。(中略) このイサナとりという言葉は、「海」の枕詞になっていて、「いさな」ということばが単独で現れることはないのである。
結局、万葉集の中のイサナとは、生きた現実のクジラのことをいっているのではなく、クジラという巨大な生き物が存在している、広いおそろしい海という、当時の人びとが何らかの知識として話に聞いていて、そこから構築した世界のことを表現しているにすぎない。これはある種のイリュージョンである。
つまり、クジラは「怖い海」をイメージさせるだけの言葉であって、現実味のある具体物ではないわけです。
同様に、万葉集・古事記には「チョウ」の記述はないとのこと。そういえば、奈良時代の作品内でチョウの記述を読んだ覚えがありません。
一方、古事記には「あきづ」(トンボのことです)に関する記述がたくさん出てきます。日本のことを「あきづ島」と称するぐらいですからね。しかし、万葉集に「あきづ」はほとんど現れない。
もちろん、奈良時代にもチョウやトンボはわんさかいたはず。これらの動物が「見えたり見えなかったりする」のは、まさに人間の持つイリュージョンによるものだというわけです。
日高先生にまとめて頂きましょう。
それは『万葉集』という古典が、当時のウムゲーブング(環境)を詠ったものではなく、万葉の人びとが彼らのイリュージョンに基づいて構築していた世界を詠ったものだからである。
ここからは私の見解なんですが、上記の話同様、万葉時代の人って、ほとんど「星」を見ていなかったんじゃなかろうかと思います。万葉集を読んでいると、「日」「夕」「月」は腐るほど出てくるんですが、星が本当に出てこない。出てきたと思ったら、中国伝来の教養を示すぐらいの話で、全くリアリティーに欠ける取り扱われ方。
日高先生の顰みにならって言えば、「万葉の人びとは、実際に夜空に輝く星を見つめることはなかった」と言えるのかもしれません。