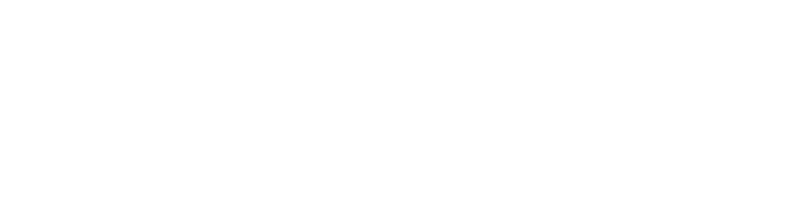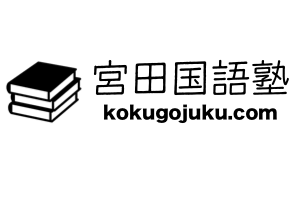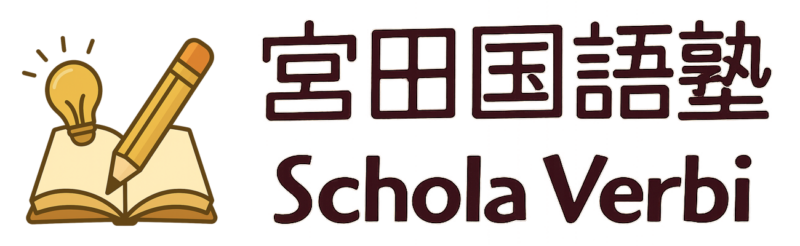朝から驚きの訃報。スティーリー・ダンのウォルター・ベッカーが2017.09.03に亡くなったとの由。67歳。惜しすぎる。
スティーリー・ダンの話はこのブログで何か取り上げた気がします。調べてみると、下記の古い記事ですね。
書きたいことがありすぎて、逆に何も書けない気がするんですが、ある一点に絞って書いてみようと思います。
「音楽に対する偏執」について、です。
私がスティーリー・ダンを思う時、一番最初に考えるのはその「偏執性」。
このスティーリー・ダン、当初は多人数編成のバンドとしてデビューしているんですが、徐々に構成メンバーは減ってゆき、割に早い時期からドナルド・フェイゲン(ヴォーカル・ピアノ)とウォルター・ベッカー(ギター)二人だけのプロジェクトになります。
この二人の音楽に対する異常な偏執性が、他のメンバーとの軋轢を生み、俺達二人だけでやったほうがいいという結論に至らせたのであろうと思います。
音楽以外の世界でもよくありますよね、ある事柄に対する「熱意」(悪く言えば「偏執」)が異なるゆえに、メンバー同士がぎくしゃくするなんてのが。そんな時は素直に別れたほうがいいと思うんですよね。どうやっても個々人の熱意・偏執を同レベルに統一することは難しいですし、仮にできたところで、でき上がるものはどこにでもある平凡なものになってしまうでしょうから。
そういう意味で、ドナルド・フェイゲンとウォルター・ベッカーの二人の選択は非常に正しかったと思います。彼らで作詞作曲し、自分たちで演奏できない・するべきでないところは、超一流のミュージシャンを呼んできて演奏させる。とても合理的なシステムだと思います。
あ、概説的なことも説明しておくほうがよいかもしれません。これはWikipediaに任せましょう。とても上手くまとまっています。
スティーリー・ダン(Steely Dan)は、アメリカのバンド。バンドのスタイルだが、事実上としてドナルド・フェイゲン (Donald Fagen) とウォルター・ベッカー (Walter Becker) のデュオとなっている。
ロックやポップスを基調としながら、ジャズ的な代理コードや意表をつくコード進行で曲にひねりを加え、一流のスタジオ・ミュージシャンを駆使した高度なアンサンブルを構築、その独特な世界観は、多くの同業者に多大な影響を与えた。テクニカルな面が強調されがちだが、1950年代のジャズやR&Bが持つフィーリングを重視しており、ドナルド・フェイゲンの個性的な歌声と奇妙で小説的な難解な歌詞との取り合わせもまた、スティーリー・ダンの個性を際立たせる非常に重要な要素となっている。
概説部分にも、やはり「一流のスタジオ・ミュージシャンを駆使」ということが明記されていますね。もちろん、ここにも彼らの「偏執性」が現れているんですが、その使い方がすごいんです。
一流のスタジオ・ミュージシャンを何人も呼び、曲のソロパートを演奏させる。一人につき何パターンもです。普通、超一流の演奏家が来れば、「お任せします」となりがちな気がしますが、彼らは、しつこいぐらいにあらゆるパターンの演奏を要求するわけです。そして揃った超一流のソロ演奏群から「ひとつだけ」を採用します。
これ、怖すぎないですか?超一流のミュージシャンをスタジオに呼びつけて、何度も何度も演奏させて、あげくの果てに、その録音は採用せず廃棄って……。音楽家としてのプライドを傷つけることになるでしょうし、「今後お前らのためには絶対に演奏せんぞ!」と言われそうですしね。
しかし、彼らの音楽に対する「偏執性」は、そんなこと意に介させなかったんでしょう。名作「ガウチョ」については、このように説明がなされています。
フェイゲンやプロデューサーゲイリー・カッツの完璧主義は前作を超え、演奏に寸分の狂いも許さず、一方ベッカーは麻薬に溺れレコーディングどころではなくなっていた。前作に比べ、膨大な時間(2年半)と費用(日本円で1億円以上)がかさんだり、曲がミスで消されるなどのトラブルが頻発したが、完成度の高さは頂点を極めている。スティーリー・ダンはこのアルバムを区切りに、長い休止期に入る。
あまりの偏執、完璧主義が度を超えて、自縄自縛に陥っていった経緯がよく分かります。
これ以外にも、レコードの音質に二人が異常にこだわっていたエピソードも残っています。二人が抜き打ちでレコード工場を訪れ、ランダムに音盤を抜き取り、音質検査をしたことがあったとか……。偏執の度合いが過ぎて恐ろしくなってくる話じゃないですか。
彼ら自身、インタビュー映像の中で、自分たちのことを「俺達、今の言葉でなんて言ったっけ、そう、「オタク」(“nerd”) だからな」と述べているので、大いに自覚はあったんだろうと思いますが。
私は高校生の頃に前述の「ガウチョ」を聴いて、もうこれ以上のジャズをベースとしたロックは現れないなと確信しました。あまりに精密なのに、あまりに生き生きとした音でしたから。今振り返ると、16歳で何が分かるのかと思うんですが、その直感はやっぱり正しかったと言わざるを得ません(口幅ったいですね、すみません)。
音楽理論的なことは分からないので、別の方に任せるしかありませんが、ジャズ・ロック?ロック・ジャズ?ソウル・ジャズ?アシッドジャズ?(名称は何でも構いません、要するに「ジャズの影響を色濃く受けたポピュラー・ミュージック」ということです)の世界において、この二人を超える人たちが出てくることはまず考えにくい。そのことだけは断言できると思います。
個人的な話になりますが(というかそればっかりですけど)、アルバム「ガウチョ」は、4回ぐらい購入しています。最初は高校生の時にアナログ盤で。何度も聴きすぎてバチバチと雑音だらけになりました。2度目はCDになった時。3度目は多分リマスターが施された時。4度目も何かの機会で購入したはず。
妻にこの話をすると、同じアルバムを何回購入するねん、バカじゃないかと言われるんですが、スティーリー・ダンの音楽はそれに値するものなんですよね。
今はウォルター・ベッカーのご冥福を祈ることぐらいしかできませんが、ドナルド・フェイゲンはどんな気持ちでいらっしゃるのか。それが気がかりです。
Steely Dan – Babylon Sisters – HQ Audio
1980年発表、Gaucho冒頭の曲。無駄なものが一つもなく、必要なものはすべてある曲。上手いとは言いがたいドナルド・フェイゲンの歌が最後のピースを埋める曲。何度聴いたか分からない曲。