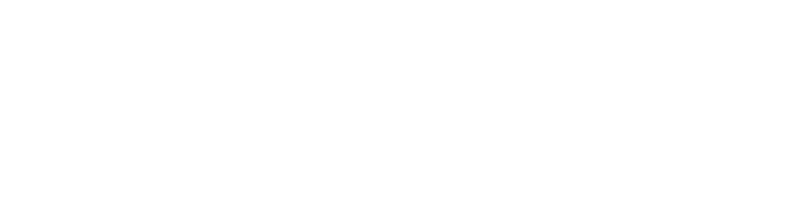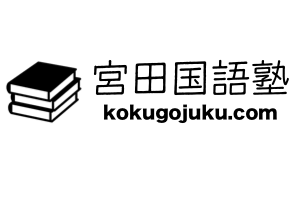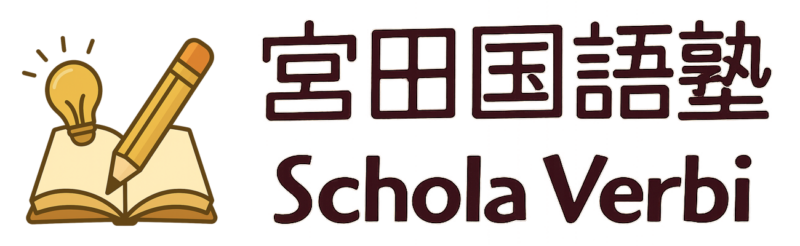ちょっとした読書メモ。
昨日、車谷長吉『贋世捨人』を読了。読み出したらグイグイ引き込まれて、随分夜更かしをしてしまいました。氏が作家になるまでの半ば自伝的な作品なんですが、どこか不思議な感覚があります。
贋世捨人(文春文庫)
車谷長吉

(冒頭部分が立ち読みできます)
正直に言えば、陰惨・卑猥・反道徳的な部分が多いので、このブログ(塾ブログなのでたまに小学生も読んでいたりします)で紹介するには全く適していない作品です。取り扱われている内容は、苦しく重く暗い。こんなことを実名で書いてヤバくないんですかと思ってしまう部分も多々あります。著名な文学者、政治家、右翼の大物、町にうごめく庶民、いずれもが徹底的に実在の固有名詞として同列に扱われ、読む者としては嫌でも興味を惹かれます。
作者だけでなく周囲の人々も、どこか澱んだ生活に身を浸していて、汚辱にまみれています。薄暗い町、家、会社。憎悪、諦念、失意、明るい感情が描かれることがほとんど無い。
しかし、何だろう、逆説的ですが、文章のそこかしこに、明朗なものが、腹を据えた人間・吹っ切れた人間の潔さのようなものが吹き渡っています。濁世に浸りきって、身を落としきるところまで落とした果てに、清澄な地平が広がっているとでも言いましょうか。そういう意味で、読後感がむやみに良かった小説なんですが、内容を考えるとそれは奇跡的なことのようにも思えます。
この世には、書かずしては生きられないという「業」を背負った人々がいますが、車谷長吉氏は正しくその一人。私のような凡人は、「業」を負う人を眺めやることぐらいしかできません。
さて、「世捨て」という生き方がこの小説のテーマ。すべての「世捨て」は「贋」だと喝破するのが、氏の母親であるところが面白い。その部分だけ引用させてもらいます。東京で失業した筆者が、無賃乗車をして故郷の姫路まで帰って来、実家でボンヤリしているシーンです。
母がそばへ来た。
「あんた、貧乏が好きになって、なれの果ては無一物や。ほら、無一物でもええわいな。どのみちこの世のことは、あの世へ持って行かれへんのやさかい。けど、人は死ぬまで生きて行かな、あかんのやでな。それにはいやでも応でも銭がいるわいな。あんた何様なんやいな。(中略) 西行はんな、あの人、何もかも捨ててもて、無一物がいっちええ、いうような歌、上手に詠んだったわいな。けど、あの人な、世を捨てたったあとも、紀州の方にようけ年貢米が上がる荘園持っとったったいう話やないか。これだけはよう捨ててなかったいう話やないか。しがみ付いとったったいう話やないか。百姓に汗水たらして働かしといて、我が身は無一物がええ、いう歌を詠む。これが西行はんいう人の性根や。(以下略)」
私も授業の中で、時々こういう話をするんですが、西行、兼好、長明に幻滅されるんですよね。いくら格好を付けても、生きてゆく以上、お金は要るし、ウ○コもするよと(尾籠な話すみません)。
私は、お金に執着しすぎるのは馬鹿らしいことだと思いますが、その一方で、「お金なんて汚らわしい」なんてお高くとまるのもまた偽善的で大嫌いです。形而上世界に生きているかのような人よりも、地面に這いつくばって生きている人の方が、やっぱり親近感が湧きます。そんな意味で、とても「爽やかな」作品でした。