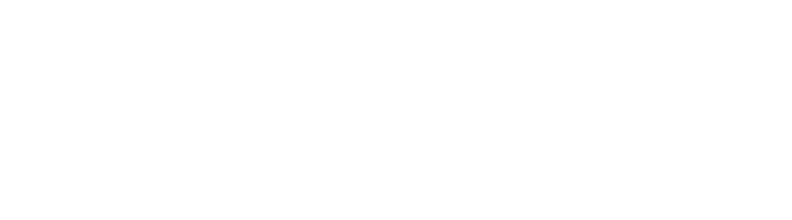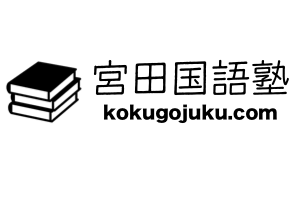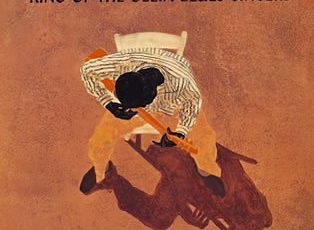楽しみにしていた映画 “Becoming Led Zeppelin” を見てきました。
はぁ〜、やっぱりレッド・ツェッペリン最高。とにかく最高。

一人で観たので、終映後妻に「俺バンド組むわ!」ってメールしたぐらいです。
妻「楽器丸っきりできないやろっ!」
私「明日ギター買いに行ってそれから練習するねん」
もちろんメールの内容は冗談ですが、それぐらい胸を撃ち抜かれました。才能にあふれた若い4人が、ロックバンドを結成し、雄々しく羽ばたいてゆき、後世に名を残すバンドとなってゆく、その軌跡に。彼らの描いた軌跡は美しすぎて、一篇の詩のような趣すら感じさせます。ドキュメンタリーなのに、何度か涙しました。
あまり詳しくない方のために一言説明しておきますと、レッド・ツェッペリンは70年代のロック界を支配した英国の4人組バンド。初期の音楽の底流にはリトル・リチャード等のロックン・ロールも流れていますが、何よりもシカゴ・ブルースの激しい濁流があります。
私的な話になりますが、私がいわゆるロックやソウルミュージックに目覚めたのは小学低学年の頃でして、もう来る日も来る日も年上の従兄にもらったテープをすり切れるほど聞いていました。中学生ぐらいからは小遣いを貯めてロック・コンサートに出かけるのが無上の喜びでしたし(先般亡くなったオジー・オズボーンもこの頃にライブを観ています)、高校生の頃には将来的に音楽評論家の道を歩もうと結構真剣に考えていたんですよね。今は何の因果か楽しく塾屋さんをやっているんですが。
そんな私にとってレッド・ツェッペリンは避けて通ることができないバンドです。彼らの作り上げた音楽は、私の血の中に流れていて、もう死ぬまでそのまま。私以上の年齢のロック・ファンはそういう人が多いんじゃないかな。欧米ロック系音楽界への彼らの影響は、どれだけ強調しても強調しすぎることはありません。
クイーンを題材にした映画『ボヘミアン・ラプソディ』が大ヒットして以降、興行ベースに乗るようになってきたのか、かなり多くの音楽映画が制作されました。特にドキュメンタリー系の音楽映画が多く上映されるようになったのは音楽ファンとして非常に嬉しいところ。
ここ数年の間に映画館で観たドキュメンタリー映画を挙げてみると、フランク・ザッパ、ジョン・コルトレーン、プリンスなんかが印象深いですね。いずれももうこの世にはいない人々達ですので、彼らの肉声でその人生観や音楽観を聞くのは本当に貴重な機会でした。
ドキュメンタリー映画ではありませんが、今年はボブ・ディランを題材にした『名もなき者』が感動的でした。私は映画館に二度足を運んだぐらいです。音楽映画ではあるんですが、ノーベル文学賞受賞者の若き日々と言ったほうが塾ブログには合うかな?
閑話休題。
レッド・ツェッペリン結成時のドキュメンタリー映画が来る、しかも現存メンバー出演&公認(今までそのような映画はなかった)。その報を聞いて以来、ずっと楽しみにしていたんですが、次のビデオを見て、Zeppathon(ゼパソン)を先週ぐらいからやってたんですよね。
レッド・ツェッペリンが彼らのアメリカ文化への貢献により、ケネディ・センターで表彰された際の映像です。俳優のジャック・ブラックがメンバーを前に祝辞を述べるんですが、愛情がこもっていてホントにいい。時の大統領オバマもにこやかに聞いています。ちょっとツェッペリンを知らないと分からない小ネタも含んでいますが……。
レッド・ツェッペリンはライブ盤を除いて公式アルバムを9作品残しているんですが、それを連続で聞くというのが、Zeppathon。ツェッペリン・マラソンというわけですね。やっぱり『I』は名作だのう、『II』ももちろん捨てがたい、『III』の後半も今になると沁みるなあ、『IV』はロック不朽の名盤としか言いようがないな(実際に世界的にそう評されている)、などとブツブツ言いながら、行ってきました某映画館のIMAXシアターへ。
若くして亡くなったドラムスのジョン・ボーナム(愛称ボンゾ)のインタビュー音声を、制作チームがオーストラリアの国会図書館から掘り出してきたらしく、彼の声を残りの3名(ジミー・ペイジ、ロバート・プラント、ジョン・ポール・ジョーンズ)が久々に耳にするシーンがあるんですが、その時の彼らの表情がなんとも言えず良かったんですよね。
懐かしい人からの嬉しい便りを手にしたような。今は亡き友に感謝するような。年老いた彼らの顔に浮かぶ何とも言えない慈しみの表情が、若かりし頃の彼らの関係を物語ります。
あとは実際の予告編を見ていただきましょう。
彼らが生まれた頃の戦後間もないイギリスの荒廃、一人一人のバックグラウンド、英国では売れていないのに米国で人気に火がついた話、英国に凱旋して観客を熱狂の渦にたたき込んだライブ映像、ジミー・ペイジの実験精神と堂々たるビジネス交渉術。ファンにとっては、もう見どころしかない感じです。ファンは今すぐ映画館に行くように。
受け入れられなかった頃の象徴的な映像として、聴衆が耳を塞いでいるシーンがありましたが(予告編でも確認できます)、まあ無理もないかなと。デカイ音に慣れていないなかったでしょうしね。私なら狂喜乱舞なんですけど(笑)。
加えて、ロックファンには有名な話ですが、当時最も権威のあった音楽雑誌ローリングストーン誌に作品を酷評される話も紹介されます。しかし、今その言説を振り返ると、評論家のポンコツさ・耳の節穴度がすごい。この作品を評価できないなら、もう評論とか雑誌とかやめたほうがいいよと言いたくなるぐらいです。
彼らの天才が奇跡のように出会い、溶け合い、激しいスパークを起こす。4つの才能が光芒を放ちながら天空を駆け抜ける。 “Becoming Led Zeppelin” はそのストーリーの序章だけですが、彼らのまばゆいビルドゥングス・ロマンと評してよいかもしれません。
ダイバーシティ重視の今の世の中、差別的なルッキズムと叱られるかもしれませんが、やっぱりロックバンドって格好よくないとダメだと思うんですよね。ルックスと言動が。
私がそう思うのは、レッド・ツェッペリンのボーカル、ロバート・プラントの影響が大きいせいでしょうね。次の映像などを見ていただければお分かりいただけるのではないかと。 “How Many More Times” のボーカルの入り、格好よすぎやろ……。 “How many more times, treat me the way that you wanna do?” 私には後ろにハウリン・ウルフの霊が見えます。この頃、プラントもボンゾも20歳そこそこって嘘やろ……。
書きたい事は山ほどあれど、今日はこのあたりで。