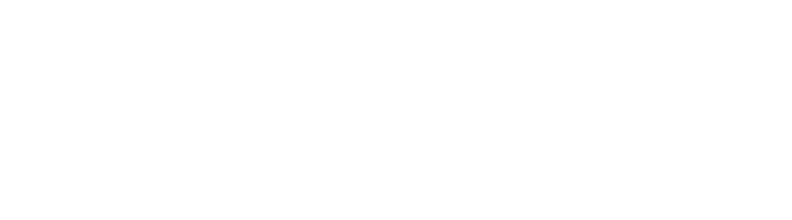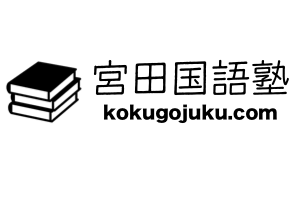私はバイクのレースが大好きですので、世界最高峰のバイクレース「MotoGP」をほぼ毎回リアルタイムで見ています。もちろんオンラインではありますが。
世界最高峰の呼び名にふさわしく、各国最高のサーキットで、各メーカーの威信を懸けて作られた最新プロトタイプモデル(一台数億円)を、世界最速のトップライダー20数名が駆り、死闘を演じるというレースでして、エリート中のエリートライダーが、文字通り「命を懸けた闘い」を繰り広げます。
文字通りというのは、F1をはるかに超える360km/hオーバーのマシンを「生身」で操り、常時「命の危険」にさらされながらバトルを繰り返すがゆえでして、常人では全く想像もできない世界での闘いです。
で、私がそのMotoGPを見ていて強く思うのは、「勝負はきわめて僅かな差でついている」ということなんです。特に近年はその傾向が強いように思います。
例えば、先週行われたサンマリノ戦、金曜日のプラクティス。MotoGPの場合、プラクティスといっても、予選の予選といった位置づけなので、ライダーはほぼ全力を出すんですが、1位と10位のタイム差は僅か「0.4秒」。「0.4秒」の間に1位から10位がひしめいている。
サンマリノはそれほど大きなサーキットではないので、MotoGPライダーは1周1分30秒台で走るんですが、彼らが全力で走れば、1秒の半分も差がつかないわけです。言い換えれば0.1秒、いや、0.01秒が勝敗を決めている。
選び抜かれたライダーたちが、限界まで作り込まれたバイクで極限走行をするが故なんでしょうが、もう素人としては脱帽と言うしかありません。
レースの話ばかりすみません。ここから塾の話に移りますね。
私が思うに、難関中学の入試も上記の状況に似ているんですよね。限界まで勉強をしてきた受験生が、最高の舞台で最高難易度の問題に挑む。中学入試の合否は結構不確かなもので、もう一度同じ受験生集団に別の問題で入試を行えば、半分程度は合格者が入れ替わるなんて話もあるぐらいです(私もそれはあり得ると思う)。
言い換えれば、1点・2点によって合否が左右されている受験生が多いイメージがあるんですよね。私の経験的にも。
「残念ながら、合格最低点に1点足りずに不合格でした……。」
「あと2点あれば最低合格点に届いていたのに……。」
こうした報告を何度も聞いたことがあります。おそらく難関校受験生を指導している人なら誰でも思い当たる節があるのではないでしょうか。
逆に、
「多分ギリギリで受かったと思います。小問をあと一つ落としてたら、おそらく不合格でした!」
「辞退があったらしく、追加合格の連絡がありました!」
これまた何度聞いたか分からない報告です。
もちろん、「何回受けても余裕で合格」みたいな規格外の受験生もいるとは思います。逆に記念受験みたいなレベルの受験生も。ただ、かなりの数の受験生は、ギリギリ合格or不合格であるという感じがします。まあ、統計学的に考えれば当然のことなんでしょうけどね。
となると、今受験校に必要な成績・偏差値がとれている人の中の大多数は、合格する可能性も、不合格になってしまう可能性もあるわけです。
では、どうすれば「合格チーム」の方に入れるのか。それはやっぱり、各学校の出題傾向にフィットすることだと思うんですよね。そこを意識的かつ徹底的にできるか。一定以上のレベルにまで勉強を進めてきた人については、それこそが極めて大きな合格のための要素になっていると思います。
だから、秋以降が受験勉強の本番です。正直に言えば、いつだって本番だと思って欲しいんですが、秋以降は「とりわけ本番になる」とでも申しましょうか……。ここからの過ごし方で合否の行方は大きく変わってくる。当塾では経験的にもそう考えています。今までの努力が実るのか、(志望校入学という意味において)おじゃんになってしまうのかは、ここからの過ごし方次第。
ということで、当塾では、ひたすら「各学校の出題傾向にフィットすること」を念頭において暮らす時期が来ました。具体的には、過去の入試問題の利活用がポイントになるんですが、このあたりはまた時間があれば詳説したいと思います。
今年も塾生の力になれるよう頑張っていきます。