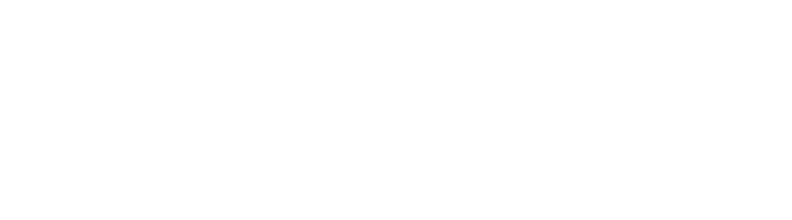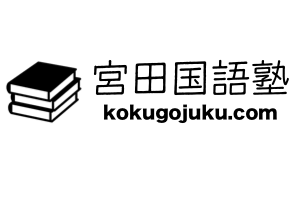小学生に文章を音読してもらうと、その国語力がよくわかるのは皆さんもご存じかと思います。文章の区切り方、読み上げるスピード、漢字の読みの正確性などなど、本当に千差万別でして、そこに小学生の国語力が如実に表れます。
国語力の高い生徒さんの場合、たいていの場合、音読しながら次のパートに視線が移っており、スムーズな読みになることが多いんですが、これは逆に言えば、音読している部分を見るのに必死で、次のパートに全く視線をやれていないような場合は、国語力が未熟であるということです。
職業柄、私たちは、ちょっと音読してもらえば、その生徒さんの国語力をほぼ正確に推知できるんですが、それぐらい、音読の力は国語力のバロメーターになっています。(もちろん、吃音のある生徒さんなどはまた別論です。当塾では吃音の生徒さんに発言や音読を求めることはありません。この話は長くなるので、また別の記事にしますね。)
今日は「音読」の中でも、特に「助詞」というパーツに絞って話を進めたいと思います。
「助詞」って、1文字2文字の本当に小さなパーツなんですが、文章の内容を大きく左右するパーツでもあります。もっと言えば、くっつく部分が文中でどのような役割を果たすかを示す超重要なパーツです。
例えばこんな感じ。
1.私は学生です。
2.私の学生です。
前者の文では、「私は」が主題・主語となっており、話している人は学生でしょう。
後者の文では、「私の」が連体修飾語となっており、話している人はおそらく教師や教授。
全然意味が異なってきますよね。
3.私は学生です。
4.私が学生です。
「私は」「私が」いずれも主語ですが、微妙にニュアンスが異なりますよね。詳しい説明は避けますが、この差異を日本語を学ぶ外国の方々に説明するのは、かなり難しい業だと思います。
こんな風に助詞や助動詞などの付属語で文法的機能を表すのが日本語という言語ですが、こうした言語を形態分類上、「膠着語(こうちゃくご)」と呼びます。「膠(こう)」の訓読みは「にかわ」。「接着剤」のことですね。単語にペタペタと接着剤で助詞・助動詞をひっつけていくイメージを持っていただければ。言語学の詳しい話は避けますが、朝鮮語やモンゴル語もこの分類に属しますので、親戚のような言語ですね(だから日本人にとって比較的学習が容易とされる)。
話が少しそれましたが、私が言いたいことはもうお分かりいただけたかと思います。
日本語を初めとする膠着語では、助詞・助動詞をおろそかにせず、キチンと読むことが、文章の正確な理解に必須です。絶対におろそかにはできない。
最初の「小学生の音読」の話に戻りますが、文章を音読してもらうと、驚くほど助詞に無頓着な小学生がいます。めちゃくちゃに読み間違えるんですね。たとえばこんな感じ。
教材文章「私は友人と海水浴に出かけた。友人はクラゲに刺されてしまった。」
生徒音読「私の友人は海水浴に出かけた。友人はクラゲが刺されてしまった。」
ちょっと待って、一文字一文字を丁寧に読もうね。「私は友人と」だよ。あと、「クラゲに刺されて」だよ。「クラゲが刺され」たらおかしいよね。
一文二文でこの状況ですから、その集合体たる文章・長文の意味が正確に把握できているはずがありません。頭の中で描かれている文章像は、グラグラに揺れている。
助詞は、いわば建築部材に使われるネジやボルトのようなものです。その一つ一つがしっかり止められていなければ、部材もその集合体である建物もグラグラになっているはずです。いや、そもそも建物の形をなしていないかも。
こんなときは焦っても逆効果です。ゆっくりしっかり読んでもらうしかありません。
いいかい?ちゃんと聞いておいてね。
私「私は!友人と!海水浴に!出かけた。友人は!クラゲに!刺されてしまった。」
はいっ!そんな感じで読んでみよっか!
生徒「私は!友人と!海水浴に!出かけた。友人は!クラゲに!刺されてしまった。」
うん、いいねっ!そんな感じで一文字一文字を大事にしようねっ!
ちょっと松岡修造が入ってます(笑)。
不思議なことなんですが、こういうケースで保護者さんが焦って「速読」を習わせることがあります。いや、ゆっくりでも読めていないのに、それを速く読めるはずがないじゃないですか……。さらに不正確度が増すだけです。
その後しばらく経過してから当塾の門を叩いてくださるケースがあるんですが、この場合、生徒さんに「文章は速く読まねばならないもの」という先入観が付着しており、これを除去するのにまた時間がかかるということもしばしば。
しっかりと丁寧に読む。細部をおろそかにせず丁寧に読む。助詞の正確性というのは、その第一歩(かつ非常に重要な一歩)だと思っています。ご自宅でお子さんの音読を聞かれるような場合は、助詞に聞き耳を立ててみてくださいね。