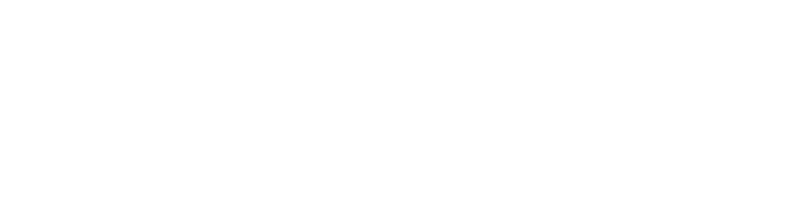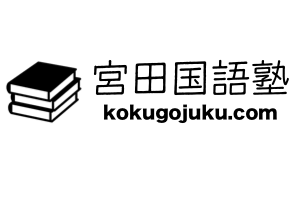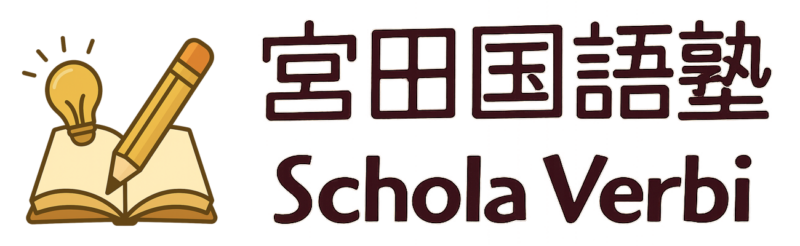お盆休み中に久々にヘルマン・ヘッセ『車輪の下』を読もうかなという気になり、入手しておいたんですが、読み始めると面白くてついつい一気読み。お盆休み開始前に読み終えてしまいました。

昔々に読んだはずなんですが、ストーリーもうろ覚え、細かい描写に関しては全くといってよいほど覚えていませんでした。ひょっとして初めて読んだかなと思うぐらいに。ただ、妻も、私の本棚に昔あったはずと申しておりましたので、読むのは多分2回目(頼りない)。
最近ラテン語にハマっているんですが(毎日のようにラテン語のことを考えています)、ある方が「ラテン語を勉強している人は嫌な気持ちになるから、絶対に『車輪の下』を読んじゃダメ」とおっしゃってたんですよね。じゃあ久々に読んでみようかなと(あまのじゃくなのです)。
田舎町の秀才ハンス・ギーベンラート君が刻苦勉励の末、選ばれし者だけが入学できる神学校に進むものの、結局は挫折していわゆるブルーカラーの道に転身、その後あっけなく死んでしまうというのが大まかなストーリーなんですが、これは筆者ヘルマン・ヘッセの半自伝的小説でもあるらしい。
内容をあまり覚えていないぐらいだったので、昔読んだ時もあまり感動しなかったのかもしれませんが、ヘッセの言いたいことは分かります。学問的な天分に恵まれた少年少女の挫折の辛さ。勉強が出来ない子も辛いだろうけれど、勉強が出来る子にも辛さはある。後者の挫折がもたらすものは意外に深い。挫折は精神的な死を呼び、時に肉体的な死をも招く。
実際この小説内でも、少人数制の学校であるにもかかわらず、ある者は放校処分を受け、またある者達は(主人公ハンスを含め)命を落とします。
ただ、どうでしょう。私のようなおっさん年齢になって読んでみると、どうもヘッセの伝えたかったであろうメッセージとは違う感想を持ってしまいます。
ハンス・ギーベンラートの天分については疑う余地がなかった。先生たちも、校長も、近所の人たちも、町の牧師も、同級生も、みんなこの少年が鋭敏な頭の持ち主で、とにかく特別な存在であることを認めていた。それで彼の将来ははっきりきまっていた。というのは、シュヴァーベンの国では、天分のある子どもにとっては、両親が金持ちでないかぎり、ただ一つの狭い道があるきりだったからである。
それは、州の試験を受けて神学校にはいり、つぎにチュービンゲン大学に進んで、それから牧師か教師になる、という道だった。年々四、五十人のいなかの少年がこの静かな安全な道を進んだ。堅信式をうけたばかりの、過度の勉強にやせた少年たちが、官費でもって古典語学中心の学問のいろいろの分野をあわただしく修めて、八、九年後には、一生の行路の――たいていの場合はずっと長い――後半にはいるのである。そして国家から受けた恩典を弁済していくわけである。
数週間後にまた「州の試験」が行われるはずだった。「国家」が地方の秀才を選ぶ例年の大いけにえはそう呼ばれている。その期間中は、試験の行われている都に向って、小さい町々や村々からたくさんの家族の溜息や祈願が集中されるのだった。
ヘルマン・ヘッセ著 高橋健二訳『車輪の下』より引用
うわ〜面白そう!合格すれば人々から尊敬され、しかも官費で(つまりタダで)学べる!古典語学、つまりラテン語や古代ギリシア語やヘブライ語の勉強も最高に楽しい!同じ目的を持った同レベルの友人達と切磋琢磨できる!おまけに将来は社会的地位の高い職業につけて食いっぱぐれがない!もうこんなん最高やん!おれ、この神学校目指すわ!
って、なんか「勉強サイコパス」みたいな感想を持ってしまったことに自分で気付いてちょっと苦笑。多分ヘッセの感覚とは大きくズレてるよね……。作中のハンス君は青白い顔をしてひたすら入試勉強に励むんですが、それは向学心というよりも虚栄心にもとづく勉学。そんなのだからしんどいんだよ。ハンス君、もっとラテン語を楽しもうぜ!なんて言っても、この気楽なおっさんは何もわかってないなと冷笑されるのがオチでしょうけれど。
ただ、ヘッセがラテン語をしっかり勉強してきた人だとわかる表現もあって、頷くことしきり。
この代数の時間はいくら勉強してもおもしろく思えなかった。暑い午後の最中に、泳ぎ場にいくかわりに、先生の暑いへやにいき、蚊のぶんぶんいうほこりっぽい空気の中で、疲れた頭をかかえ、ひからびた声で、aプラスb、aマイナスbを暗唱するのは、やはりつらかった。そしてなにかまひさせるような、極度におしつけるようなものが、宙にただよっていた。それが、悪い日には暗澹とした絶望に変りかねなかった。
だいたい、数学は彼には妙なものだった。彼はけっして、数学を解する頭のない生徒ではなかった。彼はときどき、うまい、それどころかあかぬけした解き方をした。そして自分でもそれを愉快に思った。数学には変則やごまかしがなく、問題をそれて、不確実なわき道をうろつくことのない点が、ハンスは好きだった。
同じ理由でラテン語も非常に好きだった。このことばは明瞭で、あやふやなところ、あいまいなところがなく、ほとんど疑いというものを知らなかったから。
だが、算術ではたとえ答えがみな合っても、なんにもならなかった。数学の勉強や授業は平地な国道を歩くようなものに思われた。たえず前に進み、毎日なにかしら前日までわからなかったことがわかるようになるけれど、とつぜん広い見はらしが開ける山に登るというようなことはなかった。
ヘルマン・ヘッセ著 高橋健二訳『車輪の下』より引用
数学の無味乾燥さには私も同意するんですが(笑)、逆に言えば、上記の表現は、ラテン語の学習に「とつぜん広い見はらしが開ける山に登る」ような時があることも示しています。それは私がここ半年ほど取り組んできたラテン語学習の中で何度も感じたことでもあります。ラテン語の論理明晰性について述べられているところも、心から共感を覚えます(その分難解なんですが)。
以下は挫折した主人公ハンスへの周囲の反応なんですが、これ、中学入試で全部不合格の憂き目を見た子どもや、何とか入学したものの成績がふるわず自己肯定感が全く持てない子どもにも共通するところがあるように思います。
校長からギーベンラートの父親や教授や助教師にいたるまで、義務に励精する少年指導者たちはいずれもみな、ハンスの中に彼らの願いを妨げる悪い要素、悪く凝り固まったなまけ心を認め、これを押えて、むりにも正道に連れもどさねばならないと思った。たぶん例の思いやりのある助教師を除いては、細い少年の顔に浮ぶとほうにくれた微笑の裏に、滅びゆく魂が悩みおぼれようとしておびえながら絶望的に周囲を見まわしているのを見る者はなかった。
学校と父親や二、三の教師の残酷な名誉心とが、傷つきやすい子どものあどけなく彼らの前にひろげられた魂を、なんのいたわりもなく踏みにじることによって、このもろい美しい少年をここまで連れて来てしまったことを、だれも考えなかった。
なぜ彼は最も感じやすい危険な少年時代に毎日夜中まで勉強しなければならなかったのか。なぜ彼から飼いウサギを取り上げてしまったのか。なぜラテン語学校で故意に彼を友だちから遠ざけてしまったのか。なぜ魚釣りをしたり、ぶらぶら遊んだりするのをとめたのか。なぜ心身をすりへらすようなくだらない名誉心の空虚な低級な理想をつぎこんだのか。なぜ試験のあとでさえも、当然休むべき休暇を彼に与えなかったのか。
いまやくたくたにされた小馬は道ばたに倒れて、もう物の役にもたたなくなった。
夏のはじめに郡の医者は、主として成長に基因する神経衰弱にすぎないと、重ねて診断した。ハンスは休暇中十分にたべ、さかんに森を歩き、みっしり養生するようにしたら、きっとよくなるだろうということだった。
残念ながらそこまでいかなかった。休暇になる三週間前のことだった。ハンスは午後の授業時間に教授からひどくしかられた。先生がののしり続けているうちに、ハンスはベンチにぺたんと倒れ、せつなげに震え始め、それからしゃくり上げて泣きだし、いつまでもやめず、授業をまったく中断してしまった。そのあと、彼は半日寝床に寝ていた。
ヘルマン・ヘッセ著 高橋健二訳『車輪の下』より引用
ここまで来ると、さすがに大人として、挫折したハンス君に哀れみを覚えます。ただ、もっとタフに生きて欲しいんですよね。そもそもハンスは上から2位の成績で神学校入試に合格していますし、学校での勉学をこなす能力に問題はないはずなんです。そんなに悩まなくてもいいんだよ、もっと気楽に勉強を楽しもうぜ!と(やや無責任に)思わなくもありません。
「そりゃ勉強ができるのは悪くないことだけど、しょせん勉強なんだし、出来なくてもどうってことないよ」と周りの大人たちが伝えてやればいいんですが、そういう環境に無かったのが、ハンス君の不幸だったかもしれませんね。鈍感な大人に言われても、鋭敏な少年少女には届かないかもしれませんが……。
ドイツ文学者の池内紀が帯に寄せている文章に「蝶になりそこねたサナギ」という一節がありますが、これは本当に言い得て妙。少年期から青年期への移行はなかなか難しい。
今仮に私がハンス君の立場に置かれたとしたら、キャッキャと学園生活を楽しめる気がします。どの授業も楽しそうですし、そもそも勉強ばっかりしていればいい生活なんて極楽じゃないですか。おいら、ちょっと寄宿舎学校行ってくる!(笑)。